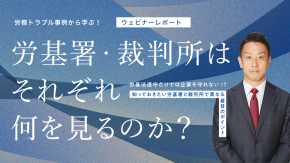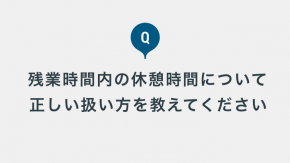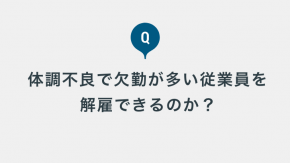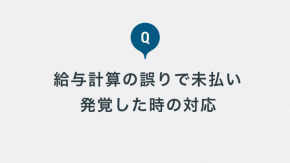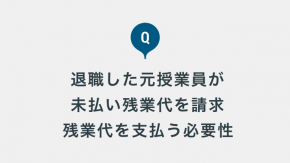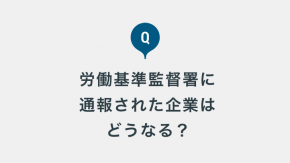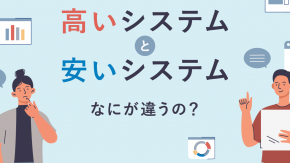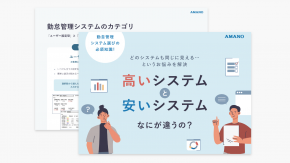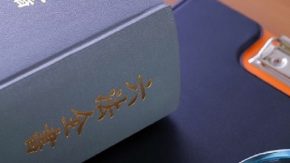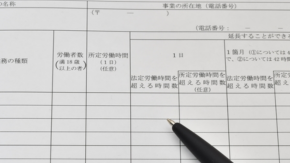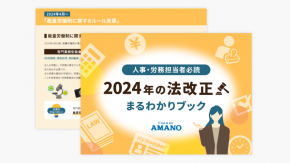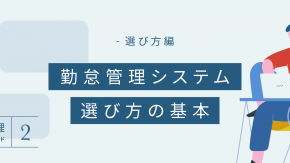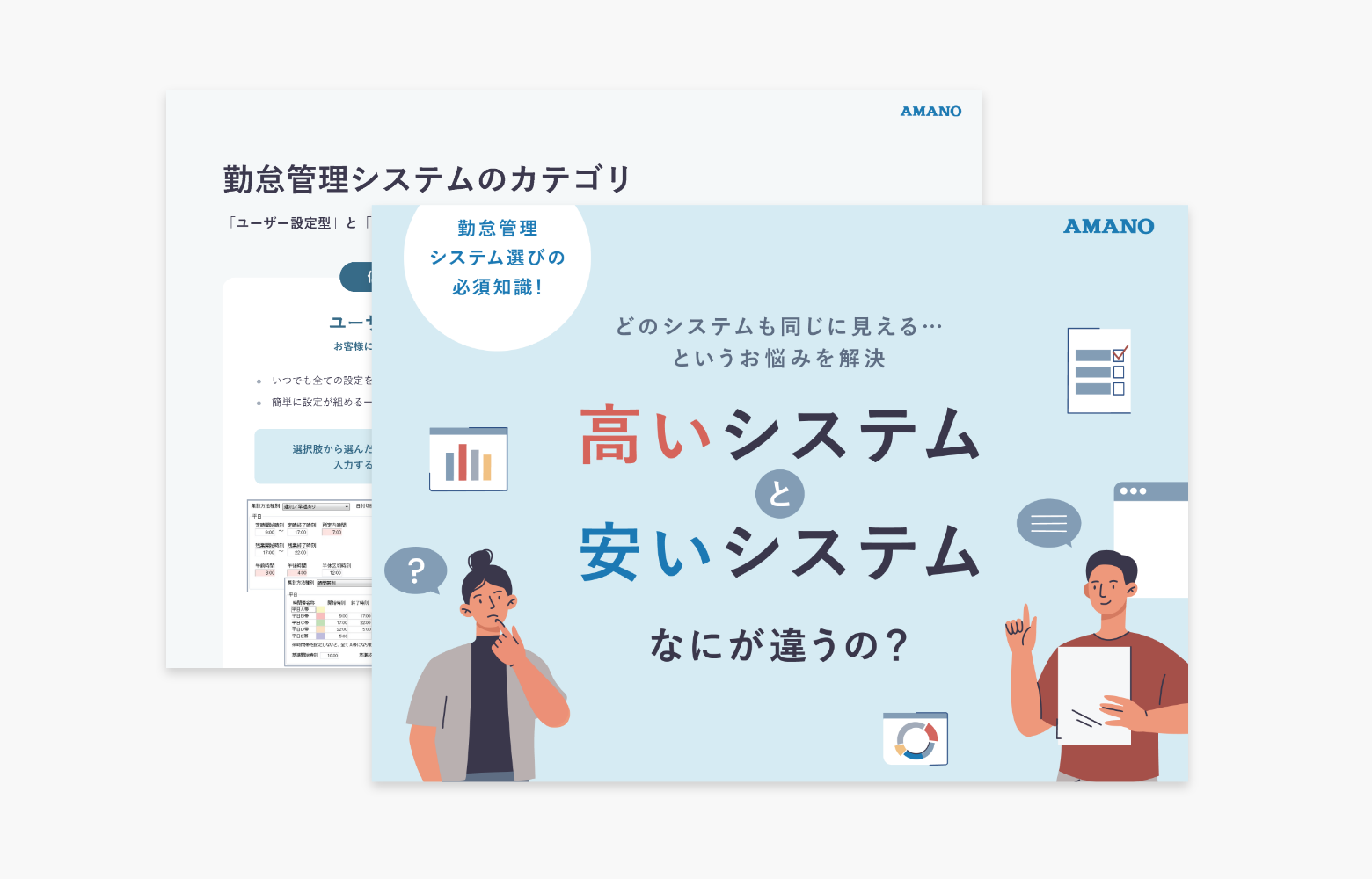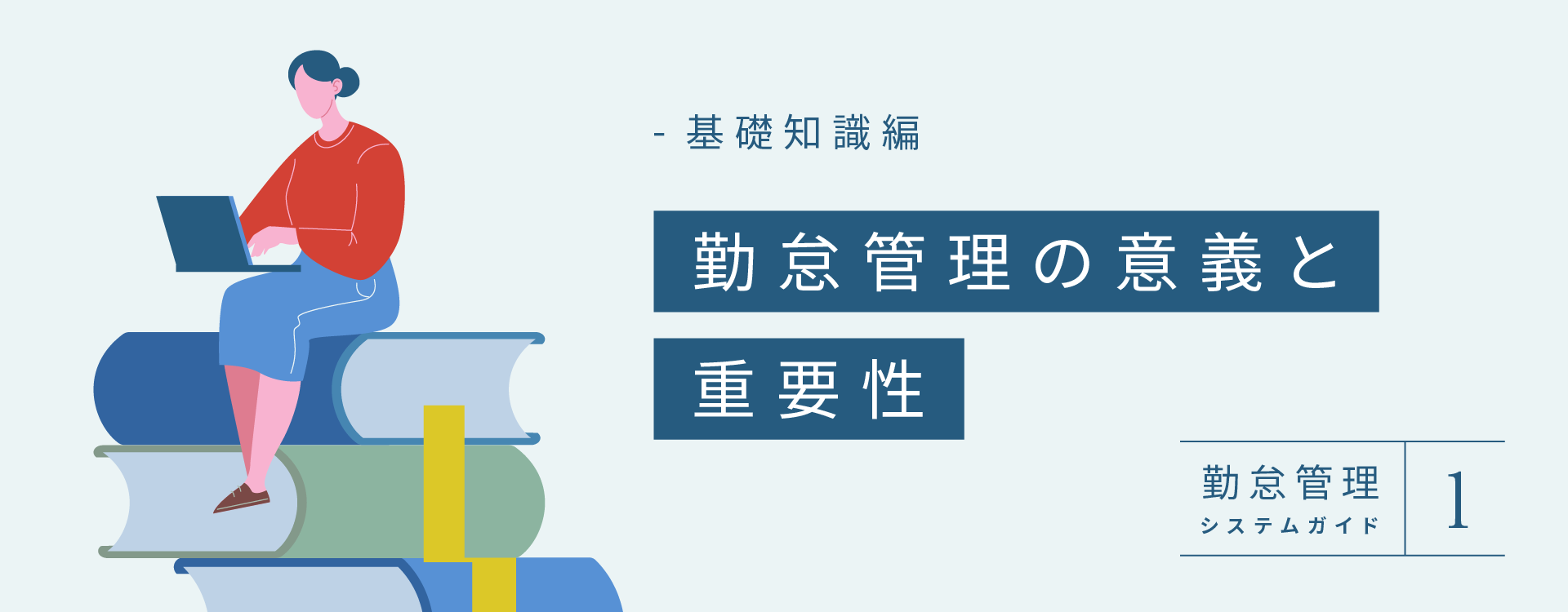
本記事では、「客観的な」勤怠管理とはなにか? を紐解きながら、勤怠管理の基礎知識について、勤怠管理システムのパイオニアであるアマノの知見を交えて解説していきます。
勤怠管理の基礎を学びたい方、改めておさらいしたい方もぜひ参考になさってください。
勤怠管理とは
勤怠管理とは、企業が従業員の勤怠情報を記録し管理することです。労働基準法では、従業員の勤務時間や残業時間、休日数などについて、会社が遵守しなければならない基準が定められています。企業が労働基準法を守り、賃金の支払いを適切に行うには、従業員の勤務日数や残業時間等を把握することが必要です。
2019年4月に労働基準法が改正され、企業には客観的な労働時間を記録することが求められるようになりました。
「客観的」な労働時間の記録とは
「客観的な」労働時間を記録するという意味は、簡単に言うと「自己申告ではない」労働時間を記録することです。厚生労働省「労働時間の適正な把握のために 使用者が講ずべき措置に関する基準」によると、
その1 始業・終業時刻の確認・記録
使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること
その2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
とあります。つまり客観的な労働時間を記録するということとは、原則として自己申告を認めず、
- 使用者自ら、または労働時間管理を行う者が直接出退勤時刻を確認する
- タイムカード、ICカード等の「客観的な記録」を基本情報として用い、記録する
のいずれかの方法をとることを言います。
原則として自己申告は認められていないものの、どうしても自己申告制を取らなければならない場合の措置も設けられています。しかし、同資料で「自己申告による労働時間の把握については、あいまいな労働時間管理となりがちであるため、やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を把握する場合に講ずべき措置を明らかにしたものです」とあるように、あくまでも他に方法がない場合の措置であり、推奨されていない方法であるということは理解しておきましょう。
勤怠管理の対象
勤怠管理の対象となるのは、以下の企業・従業員です。
勤怠管理の対象企業
勤怠管理の対象となる企業は、「労働基準法のうち労働時間に係る規定(労働基準法第4章)が適用される全ての事業場」と定められています。
ただし、天候などに左右される農漁業は、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用外となる場合があります。
勤怠管理の対象となる従業員
勤怠管理の対象者は、「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての労働者」と定められています。
以下の場合を除けば、雇用形態や職種にかかわらず、ほぼすべての従業員が勤怠管理の対象となります。
管理監督者
労働基準法第41条に基づき、経営者と一体的な立場で仕事を行う管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外となります。管理監督者の該当性は複雑ですが、行政解釈では「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断する」とされています。
ただし、労働基準法第39条に定める年次有給休暇の規定は適用されるため、有給休暇取得状況の管理は必要です。
裁量労働制の適用者
労働基準法第38条の3(専門業務型裁量労働制)および第38条の4(企画業務型裁量労働制)に基づき、裁量労働制が適用される従業員は、実労働時間ではなく協定等で定めた時間働いたものとみなされます。ただし、労働安全衛生法に基づく健康管理の観点から、労働時間の状況把握は必要です。
事業場外労働のみなし労働時間制適用者
労働基準法第38条の2に基づき、事業場外で労働する従業員で労働時間の算定が困難な場合、みなし労働時間制が適用されることがあります。この場合、みなし時間に関しては通常の勤怠管理の対象外となりますが、実際の労働時間の把握は求められます。
ただし、労働安全衛生法上は”すべての従業員”について労働時間を管理・把握する必要があるため注意が必要です。詳しくは下記の記事をご確認ください。
勤怠管理で把握すべき項目
勤怠管理で把握すべき項目は、主に以下の6つに分けられます。
労働時間(出退勤時刻)
従業員の実際の労働時間を正確に記録します。出勤・始業時刻と退勤・終業時刻を把握し、所定労働時間との差異を管理します。
休憩時間
法定の休憩時間が適切に取得されているかを確認します。労働時間に応じた休憩時間の付与が必要です。
時間外労働・深夜労働・休日労働
企業が定める所定労働時間を超える労働を正確に記録し、過重労働を防止します。特に、1日8時間、週40時間の法定労働時間外の労働は割増賃金の対象となるため、適切な把握が大切です。
有給休暇の取得状況
従業員の有給休暇の取得状況を管理し、適切な取得を促進します。法定の年次有給休暇の付与と取得促進が求められています。
欠勤・遅刻・早退
欠勤、遅刻、早退の記録を適切に管理し、必要に応じて対応を行います。
育児・介護休暇など
育児休業や介護休業など、特別な休暇の取得状況も適切に管理します。
勤怠管理が必要な理由
企業が勤怠管理を行う主な目的は以下のとおりです。
従業員が安心して働ける環境づくり
従業員の労働時間を正確に把握することで、労働時間の調整や仕事の配分を適切に行うことが可能になり、業務の集中によるメンタルヘルス不調を未然に防ぐことができます。現在の勤怠状況を可視化することで、従業員一人ひとりに合った働き方の見直しができるようになり、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
人件費の正しい把握
勤怠管理を行うことによって、従業員一人ひとりや部署ごとの毎月の労働時間が可視化され、それに伴う人件費がどれくらい発生しているかが分かります。人件費がどれくらい発生しているかを正確に把握できれば、効率化すべき業務がどの部署にあるのか、配置転換やツールの導入で必要以上に発生している人件費の削減を検証できるなど、業務効率化に役立ちます。
過重労働の早期防止
勤怠管理によって、社内で誰がどのくらい長時間労働をしているかが可視化されるため、過重労働の早期発見・防止につながります。過重労働の早期防止は、従業員の健康悪化や36協定違反を防ぐ上でも非常に重要です。また、過重労働が発生しやすい部署や時期を把握しておけば、部署の人員を増やしたり、業務フローを見直したりといった是正対策も立てやすくなります。
正確な給与計算
従業員の労働時間や休日数を集計し、給与計算を行うには出退勤や労働時間の記録を正確なデータとして残しておくことが必要です。打刻ミスをはじめ不正確な勤怠管理が行われている状態では、毎月の給与計算業務を円滑に行うことができず、給与の支払いに影響が出る可能性があります。適正な勤怠管理は、自社の給与計算を正確かつスムーズに行う前提条件と言えます。
コンプライアンス違反防止
給与計算に必要な集計だけではなく、労務トラブルや違反の防止も勤怠管理の重要な役割です。勤怠管理には労働基準法をはじめとする法律に従い、従業員の働き方や労働時間に問題がないか管理することで企業のコンプライアンスを遵守する目的があります。労働基準法では1日8時間以上、週40時間以上の法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合、経営者は労働組合または労働者代表と36協定を結ばなくてはなりません。不正確な勤怠管理によって未払い残業が発覚したり、過重労働が原因の過労死が起きたりすれば、重大なコンプライアンス違反となり、訴訟リスクだけでなく社会的信用を失う事態に発展することもあります。これらのコンプライアンス違反を未然に防ぐためにも、企業は適正な勤怠管理を行わなければなりません。
勤怠管理を怠った場合のリスク
勤怠管理を怠った場合、正しい勤怠管理ができていなかった場合は、企業にとって以下のようなリスクがあります。
労務トラブルの発生
不適切な勤怠管理は、企業と従業員間の労務トラブルを引き起こしかねません。未払い残業代の請求や労働条件に関する紛争、過重労働の見逃しなどのリスクを伴います。
労働基準監督署の調査
勤怠管理を適切に行っていない場合、労働基準監督署の調査対象となる可能性があります。調査の結果、法令違反が見つかれば、是正勧告や罰則の対象となる場合があります。
企業イメージの低下
勤怠管理の不備が原因で労務問題が発生した場合、マスコミの報道などにより企業の社会的信用が低下するおそれがあります。採用活動や取引先との関係などに大きな悪影響が及ぶでしょう。
勤怠管理の主な手法
勤怠管理の手法には、特別な設備がなくても導入できる出勤簿やExcelでの管理、厚生労働省のガイドラインで推奨されているタイムカードや、勤怠システムでの管理が存在します。それぞれの手法の特徴やメリット、デメリットを解説します。
出勤簿(ガイドライン非推奨)
主に紙の出勤簿に筆記用具で出勤した日付や出退勤時間を記録する方法です。
メリット
インターネット環境が整っていない場所や、PCが十分に行き渡っていない店舗や事業所、野外で作業を行う業種で利用できます。コストをかけず簡単に出退勤記録を残せることがメリットです。
デメリット
一方、記入漏れやミスが発生しやすく、従業員が個人で出勤簿を管理する場合には不正行為の防止が難しい点がデメリットです。厳密には正確な労働時間の把握ができないことから厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の中では推奨されていません。また、労働時間の集計を担当者が給与ソフトに手動で入力する必要があるため、給与計算に多くの手間と労力がかかります。
Excel(ガイドライン非推奨)
Excelシート上に従業員自身が出退勤の時間を入力する勤怠管理の方法です。
メリット
PC操作が可能な環境であれば簡単に導入できます。主にデスクワークを行うオフィスで採用されている方法です。
デメリット
しかし、基本的に労働時間は自己申告であるため、客観的な労働時間管理はできません。従業員が実際より労働時間を多く申告したり、上司の命令で少ない労働時間の申告を強いられたり、といったケースを完全に防ぐことができないというデメリットがあります。そのため、Excelによる勤怠管理は出勤簿と同じく厚生労働省の労働時間把握のガイドラインでは推奨されていません。
タイムカード(紙カード)
専用のタイムレコーダーによってタイムカードに出退勤時刻を打刻する勤怠管理方法で、従業員が少人数の企業では主流の勤怠管理方法です。
メリット
コンセントに差し込めば、購入したその日から使い始めることができます。出退勤の時刻を元にその日の労働時間を集計することができる集計タイプのタイムレコーダーもあります。また、レコーダーによる打刻を行うため、出勤簿やExcelによる自己申告の勤怠管理よりも客観的な勤怠記録として認められています。
デメリット
だたし、タイムカードの出勤・退勤の記録以外の日々の勤務時間や残業時間、給与計算は手動で転記作業を行う必要があること、タイムカードを保管する場所が必要などのデメリットもあります。また、あくまで出退勤の記録を客観的に記録することを目的としているため、1日の勤務時間の把握ができずに、過重労働を見過ごしてしまい、間違った給与計算をしてしまう危険性など、コンプライアンス違反を完全に防ぐことはできません。
勤怠管理システム
勤怠管理を行う方法の中で、最も効率的に従業員の勤務時間を記録できるのが勤怠管理システムです。近年ではインターネット環境があればどこでも出退勤記録が残せるクラウド型の勤怠管理システムが主流であり、客観的かつ正確な勤怠管理が可能な方法として広く普及しています。
メリット
勤怠管理システムの場合、PCの画面上で従業員が打刻した出退勤記録をリアルタイムで把握することができるため、従業員の出退勤状況や労働時間の合計がひと目で分かります。労働時間の自動集計機能によって、残業時間のチェックも簡単に行えるほか、給与計算システムとの連携で毎月の給与計算作業も効率化できます。サービスによっては、スマートフォン、タブレット端末、ICカード、生体認証など複数の打刻方法を選ぶことができ、場所を選ばずいつでもどこからでも打刻ができます。
また、データ修正履歴の確認やPCのログオン・ログオフ時刻と出退勤時刻との対比が可能なシステムもあり、不正や改ざん防止に有効です。
デメリット
デメリットの少ない勤怠管理システムですが、システムによって導入・ランニングコストやカスタマイズ性が大きく異なる点に注意が必要です。
勤怠管理方法のメリット・デメリット
| 客観性 | 人的ミス防止 | 不正・改ざん防止 | 利便性 | 導入のしやすさ | |
| 出勤簿 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |
| Excel | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ○ |
| タイムカード | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 勤怠管理システム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
勤怠管理システムの導入メリット
勤怠管理システムを導入するメリットについて、勤怠管理に付随する作業の効率面や不正防止の面からさらに詳しく解説します。
法令遵守の徹底
勤怠管理が杜撰だと、従業員から長時間労働による法令違反の訴えを受けたり、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性が高くなります。勤怠管理システムを導入する最大の目的は、従業員の勤怠管理を正しく効率的に行い、法令違反リスクを回避し、企業と従業員の両方を守るということです。
2019年から施行された働き方改革関連法により勤怠管理に関する法律が大幅に改定されたことから、アナログでの管理がさらに困難になりました。システムを導入することで、法改正に係る時間管理が正確に行え、労務担当者が知らないうちに法令違反を犯してしまう事態を防ぐことができるようになります。
勤怠管理を効率化
勤怠管理システムを導入すると、担当者の手間を減らしながら正確な勤怠管理ができるようになります。例えばアマノの勤怠管理システムでは、打刻漏れや長時間労働、法令違反を自動で知らせるアラート機能を備えており、これらの確認作業の手間を低減できます。また、集計作業の自動化により、業務の大幅な効率化や人的ミスの削減につながります。
さらに、サービスによっては、給与計算や申請業務など労務・人事・総務担当者が行うさまざまな業務の負担を減らすことができます。
給与計算を効率化
タイムカードや出勤簿、Excelで勤怠管理を行っている場合、労働時間を集計した後に、給与計算ソフトへデータを入力し直さなければなりません。手動による入力はミスが起きやすく、また全従業員分の労働時間の入力は毎月多大な業務工数が発生します。一方で給与計算との連携が可能な勤怠管理システムなら入力の手間が省けるだけでなく手入力によるミスを防ぐことができます。故意ではない給与計算ミスが原因であっても、給与が支払われず給与未払いとなれば労働基準法違反に該当します。つまり、勤怠管理システムを導入することで法令違反を防ぐことができるようになります。
勤怠管理システムの多くは、出退勤記録と労働時間をCSVデータで出力する機能が備わっています。CSVデータを給与ソフトに取り込むことで、勤怠データを給与ソフトへ手入力する業務が不要となり大幅な業務効率化が見込めます。また、勤怠管理システムの中には給与ソフトと一体型のものが存在し、その場合は手入力の必要なく給与計算までシームレスに行えます。
勤怠管理システムを選ぶポイント
勤怠管理システムを選ぶ際は、以下のポイントを押さえておきましょう。適切なシステムを選ぶことで、より効率的な勤怠管理を実現できます。
自社の規模や業務形態への適合性
従業員数や事業所の数、業務の特性に適したシステムを選ぶことが重要です。小規模企業向けのシンプルなものから、大企業向けの高機能なものまで、勤怠管理システムにはさまざまな選択肢があります。
クラウド型とオンプレミス型の比較
クラウド型は初期投資が少なく、迅速な導入が可能です。一方、オンプレミス型はカスタマイズ性が高く、セキュリティ面でも安心感があります。自社のニーズと状況に合わせて選択しましょう。
必要な機能の確認
残業管理や有給休暇管理、届出のワークフローシステム、アラート機能など、必要な機能を洗い出し、それらをカバーできるシステムを選びます。必要機能を洗い出す際は、表面的な対応可否だけでなく、「どのように実現が可能か」まで確認することをおすすめします。また、将来的なニーズも考慮に入れるとよいでしょう。
また、勤怠管理システムはコストにより性能が異なりますのでご注意ください。
詳細は以下の記事をご参照ください。
ほかのシステムとの連携
給与計算システムや人事システムとの連携が可能かどうかを確認します。シームレスな連携ができれば、人事・労務にかかわる業務全体の効率が大幅に向上します。
導入後のサポート体制
システム導入後のトラブルやアップデートに対応できるサポート体制があるかを確認します。継続的なサポートは、システムを長期的に活用するうえで非常に重要です。
これらの観点から総合的に判断し、自社に合った勤怠管理システムを選定しましょう。ただし、現実的に予算や仕組み的な問題で導入が難しい場合もあると思います。無理に大規模なシステムを入れずとも、まずはスモールスタートから進めるのもおすすめの方法です。アマノでは、さまざまな企業規模やニーズに合わせた勤怠管理システムを多数取りそろえています。まずは手軽な導入をご希望の方も、ぜひご検討ください。
正しい勤怠管理のポイント
最後に、正しい勤怠管理のポイントを、労働基準監督署・裁判所対策の視点を交えながら解説します。
労働基準法の理解と遵守
労働時間、休憩、休日に関する規定を正しく理解し、遵守することが重要です。特に、法定労働時間や時間外労働の上限規制について熟知しておく必要があります。
36協定の適切な締結と運用
時間外労働や休日労働を行う場合、36協定の締結が不可欠です。協定の内容を従業員に周知し、定められた上限を遵守することが重要です。また、管理監督者の範囲を適切に定める必要があります。多くの企業で管理監督者の範囲を広く取りすぎている傾向がありますが、裁判所の判断基準は厳格です。
最新の法改正への対応
労働基準法以外にも、人事・労務に関連する法律は頻繁に改正されるため、最新の法改正内容を常に把握し、迅速に対応することが重要です。法改正に適切に対応することでコンプライアンスリスクを低減し、従業員の労働環境改善につなげられます。
アマノでは、法改正のポイントや企業の対応策について順次解説しています。ぜひ参考にしてください。
従業員への周知と教育
勤怠管理の重要性や正しい記録方法について、定期的に従業員研修を行いましょう。特に、残業時間の申請や休憩時間の取得について、従業員の意識を高めることが重要です。例えば、退勤打刻後も働いている従業員が「自身が好きで残っている」ケースであっても、会社が黙認していれば労働時間として認定される可能性があります。わかりやすいマニュアルの作成や定期的なアナウンスを行い、認識を合わせましょう。
適切な勤怠管理システムの選択
適切な勤怠管理システムの選択は、正確な労働時間の把握と法令遵守の両立において極めて重要です。前述した比較ポイントを参考に、自社に合った最適なシステムを選びましょう。
労働時間の客観的な記録ができることはもちろん、PCログや入退室記録との連携機能、乖離時間の自動検出と乖離理由の申請機能など、より詳細な労働時間管理が可能なシステムを選択することが望ましいでしょう。これにより、万が一の労働基準監督署の調査や裁判所での訴訟に備えた証拠保全も可能になります。
まとめ
働き方改革関連法が施行されるのに伴い、勤怠管理の重要性は広く認知されました。使用者は、従業員の労働時間について「客観的」に記録することが義務付けられ、従来の方法では対応できなくなってしまった企業も少なくありません。
コンプライアンス遵守はもとより、従業員の労働環境を健全に保つことや人事総務労務の業務効率向上、人的ミスによる労務リスク防止のためにも、勤怠管理システムの導入は効果的です。
ただし、一度にすべての課題をクリアしようとすると膨大なコストがかかってしまうため、課題の優先度を明確にしてからシステム導入を検討するようにしましょう。
アマノでは、「TimePro(タイムプロ)シリーズ」を中心に、クラウドからオンプレミスまで、幅広い勤怠管理システムをご用意しています。労務リスク対策、業務効率化、人事給与システムとの連携など、企業規模やニーズに合わせた最適なシステムをお選びいただけます。
また、90年の実績に基づく豊富な標準機能と独自の高度な演算式技術により、複雑な就業規則にも柔軟に対応します。さらに、全国約70拠点の専門SEによる手厚いサポート体制で、導入から運用まで安心です。勤怠管理システムの導入・リプレイスをご検討中の方は、ぜひ以下の製品ページをご覧ください。
-

勤怠管理ガイド 2021.08.20
-

勤怠管理ガイド 2021.08.20
-

勤怠管理ガイド 2022.11.10