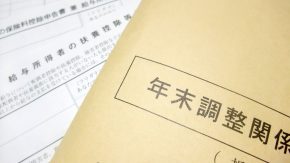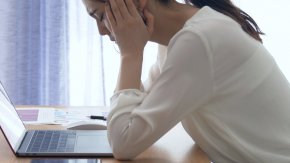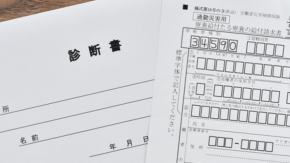過労死ラインを超える労働を課す企業は、労働基準法の違反により罰則を科せられたり、賠償を求められたりするリスクがあります。企業は過労死ラインを正確に理解して、従業員の過労死や心身の不調を引き起こさないよう配慮し、労務管理を徹底しなければなりません。この記事では、過労死ラインの要件やリスク、従業員の過労を防ぐためのポイントを紹介します。
過労死ラインとは
過労死ラインとは、健康に害をおよぼす可能性のある長時間の時間外労働を表した言葉です。過労死ラインの目安を超えた労働を課されていた従業員が健康障害を受けた場合には、労災認定を受ける可能性が高くなります。具体的には、過労死ラインは次のような水準となっています。
- 発症前2か月間~6か月間にわたって1か月当たりの時間外労働が80時間を超える
- 発症前1か月間に1か月当たりの時間外労働が100時間を超える
過労死ラインが定義される前は、脳疾患や心臓疾患と労働の因果関係が不明瞭でした。そのため、過労による労災認定がされにくかったのです。過労死ラインの定義により、健康障害が生じた従業員の労災認定が進んでいます。
なお、過労死ラインを下回っていればよいというものではありません。厚生労働省の見解では、残業時間が月平均45時間を超えて長くなるほど、健康障害のリスクが高まるとされます。企業の経営者・管理者は従業員の長時間労働の是正を徹底し、特に過労死ラインへの到達は絶対に避けなければなりません。
過労死とは
過労死とは、労働による心身の負担・ストレスが原因となって死亡に至る事象をいいます。狭義には過労が原因で脳疾患・心臓疾患などを発病し死に至る状態をいいますが、広義には過労を苦にした自殺である「過労自殺」を含める場合もあります。
過去には労働と健康障害・自殺との因果関係が不明瞭な時期がありましたが、1961年に脳疾患・心臓疾患の労災基準が設定されました。1978年に正式に「過労死」の定義がまとめられて以降、遺族の活動や医師の研究などを通じて、過労死問題が世間に広まりました。
働き方改革の浸透により長時間労働の是正が進めば、過労死も減ると期待されますが、これまでのところ、劇的な改善はみられていません。
労災認定基準とは
労災認定基準とは、労災保険給付を受けるための認定基準です。労災とは労働災害の略称で、業務遂行のための労働に起因して発生した疾病や負傷、死亡を指します。労災認定するためには、従業員の負傷・疾病などが本当に業務の結果発生した事象なのかを判断しなければなりません。
具体的には、労災認定は次の要件によって判断されます。
業務遂行性
従業員が負ったケガおよび病気が、事業主や管理者の支配下にあり業務を行っている時間中に起きたかどうかの判断基準です。オフィスや事務所内にいなければ認定されない、ということではありません。通勤・帰宅時間や、業務上必須の事情で外出している時間など、業務を遂行していれば当然発生する移動中も業務遂行性は充足します。
業務起因性
業務起因性とは、仕事をしていたことが原因で発生したケガや病気なのかを判断する基準です。
たとえば、工場で働いていて機械に手を挟まれてケガをした場合、工場での業務に従事したタイミングで発生した事故なので、「業務遂行性」に疑いはありません。また、業務の一環として機械を操作した結果発生した事故なので、「業務起因性」も充足する可能性が高いでしょう。
突発的に発生する事故と異なり、過労は心身の疲労の蓄積の結果、発生するものです。かつては業務起因性を充足するかどうかの判断が難しく、労災認定されにくいという課題がありました。過労死ラインの定義によって、近年は過労死や過労に伴う健康障害の労災認定が進んでいます。
なお、精神面での不調による労災基準や認定も近年進んでいます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
過労死ラインの見直しの内容は?
2021年7月に、厚生労働省が設置した有識者検討会が過労死の認定基準見直しについての報告書をまとめました。同報告書をもとにした新たな労災認定基準が全国の労働基準監督署に通知され、同年9月より運用がスタートしました。
以前の過労死認定基準は2001年に定められたもので、20年間大きな変更はありませんでした。2021年の改正においても、過労死ライン自体の時間外労働時間に変更はありません。一方で、過労死ラインの超過が労災認定の絶対要件ではなくなったことと、労働時間以外の負荷要因も考慮されるようになったことが、主な変更点です。
現在運用されている最新の過労死ラインについて、詳しく解説します。
過労死ラインは従来と変わらない
2021年の検討会では、過労死ライン自体は従来の水準が維持されました。医学的知見から現行の基準は妥当性があると判断されたためです。
ただし、引き下げを求める意見も根強くあります。「時間外労働が月65時間に及ぶと脳・心臓疾患のリスクが高まる」とする世界保健機関(WHO)と国際労働機関(ILO)の共同調査の指摘を踏まえて、検討委員会の弁護士や過労死遺族は過労死ラインを65時間に引き下げるべきだと主張しています。
過労死ラインを超えなくても労災と認める
過労死ラインは従来の基準で維持されるものの、2021年の見直しによって、基準に近い時間外労働の実態があり、労働時間以外の負荷が認められる場合には労災認定されるようになりました。
労働時間以外の負荷として、出張の多い業務や深夜勤務などが挙げられます。ただし、負荷がかかっていたかどうかの評価基準は、発症した従業員本人ではなく、同じ職場で立場や職責、職種、年齢、経験などが類似する従業員にとっても過重な労働であるかが重視されます。
労働時間以外の負荷要因が新たに4つ追加された
従来の労災の認定基準では、労働時間以外の負荷要因も考慮されます。2021年の見直しにより、負荷要因として新たに「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い勤務」「身体的負荷を伴う業務」「事業場外における移動を伴う業務」の4つが追加されました。
4つの要因による心身への負荷が過度に高いと判断されれば、たとえ労働時間が過労死ラインに達していない場合でも、健康障害や過労死が労災認定される可能性があります。
| 労働時間以外の負荷要因 |
| ・勤務時間の不規則性 ―拘束時間の長い勤務 ―休日のない連続勤務(新) ―勤務間インターバルが短い勤務(新) ―不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務 ・事業場外における移動を伴う業務(新) ―出張の多い業務 ―その他の事業場外における移動を伴う業務 ・心理的負荷を伴う業務 ・身体的負荷を伴う業務(新) ・作業環境 ―温度環境 ―騒音 |
休日のない連続勤務
連続勤務が長く続くほど業務と発症の関連性を強めると認められた事例もあり、2021年の見直しで負荷要因「勤務時間の不規則性」に追加されました。休日のない連続勤務が脳・心臓疾患の発症に関連したかは、連続労働日数や連続労働日と発症の近接性、休日数、実労働時間などの観点から判断されます。このとき休日が十分確保されていた場合、疲労は回復・回復傾向にあると踏まえて労災認定の際に評価されます。
勤務間インターバルが短い勤務
勤務間インターバルとは、終業から翌日の始業までの間に一定時間の休息時間を設ける制度のことです。「勤務間インターバルが短い勤務」について、脳疾患や心臓疾患の発症との関連は確認されていません。しかし、勤務間インターバルが11時間未満と少ないと、脳・心臓疾患の発症と関連がある睡眠時間不足につながります。そのため、負荷要因「勤務時間の不規則性」に追加されました。
勤務間インターバルが短い勤務についての脳・心臓疾患発症への関連性は、業務内容や時間数、頻度などの観点から判断されます。
勤務間インターバルの詳細は、以下の記事をご覧ください。
身体的負荷を伴う業務
「身体的負荷を伴う業務」は、従来は負荷要因として挙げられていませんでしたが、2021年の見直しで、疾患との関連性や過去に身体的負荷を評価した裁判例がある点を踏まえて追加されました。身体的負荷が脳・心臓疾患の発症に関係したかは、作業の種類や強度、量、時間などから判断されます。また、事務職のように本来は身体的負荷のかからない業務に従事する従業員に対しては、一般的な負荷からの逸脱度合いで判断されます。
事業場外における移動を伴う業務
「事業場外における移動を伴う業務」は、これまでも考慮されていた「出張の多い業務」をさらに明確化する目的で追加されました。見直しでは、「出張」に該当しない事業場外における移動を伴う業務も含め、負荷要因の整理が行われました。出張以外にも長距離輸送の業務に従事する運転手や航空機の客室乗務員など、通常の勤務として移動を伴う「その他の事業場外における移動を伴う業務」も「事業場外における移動を伴う業務」に含まれ、労災認定の際、負荷要因として評価されます。
過労死ラインを超えた場合
過労死ラインを逸脱した場合、労働基準法の違反が疑われます。違反が指摘されれば罰則が科されるでしょう。そのほかにも、労災に伴う損害賠償リスク、離職率の増加や企業イメージの低下といった悪影響が懸念されます。
労働基準法違反が疑われる
過労死ラインを超える従業員がいる場合、労働基準法に違反している可能性が懸念されます。労働基準法では、従業員に法定労働時間を超えて時間外・休日労働させる場合、36協定を労使間で締結し労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。36協定を結んでいても、時間外労働の上限は月45時間・年360時間と定められています。
例外として、法律上は過労死ラインに当たる月80時間の時間外労働も可能となる場合もありますが、労使の合意で結ぶ特別条項が必要です。
36協定と特別条項で規定される時間外労働の上限は以下のとおりです。
| 36協定と特別条項で規定される時間外労働の上限 |
| ・36協定を結んだ場合でも時間外労働の上限は 「月45時間・年360時間」 ・特別条項付きの36協定を結んだ場合でも時間外労働の上限は 「年720時間以内」 「複数月平均80時間以内(休日労働を含む)」 「月100時間未満(休日労働を含む)」 「月45時間を超えることができるのは、年6回まで」 |
すなわち、労働基準法を遵守していれば、過労死ラインを超えにくいしくみとなっています。管理職・高度プロフェッショナル制度対象者など、残業規制が適用されない従業員が過労死ラインを超えていれば、その時点で労働基準法違反が疑われるでしょう。なお、残業規制が適用されなくても、過労死ラインは労災認定の判断軸として機能します。管理職・高度プロフェッショナル制度対象者についても、労働時間の管理を怠ってはなりません。
損害賠償リスク
過労死ラインを逸脱した結果、従業員の心身の健康障害や死亡などが引き起こされた場合、本人および遺族から損害賠償を求められるリスクが高まります。そもそも労働基準法に違反していれば、当然ながら被害者への賠償要件となる可能性が高いです。また、労働基準法に違反していない場合でも、労災認定されるほどの心身への負荷が高い労働環境を看過していた責任を問われかねません。最終的に賠償支払いに至らなかったとしても、訴訟対応による事業の停滞、企業イメージの悪化などの影響は避けられないでしょう。
離職率の増加
過労死ラインを超過するほどの労働を課される従業員が増えれば、離職率の上昇につながる懸念もあります。過労死や体調を崩した従業員の事例を見聞きして、「自分も深刻な事態になる前に転職しよう」と考えるのは自然な流れです。また、従業員の心身の健康に配慮しない経営方針・労務管理の方針に嫌気をさして退職者が増えるおそれもあります。離職率が高まれば、人手不足が深刻化し、さらに従業員に長時間労働を課さなければならない悪循環に陥るおそれもあります。
企業イメージの悪化
過労死の発生が世間に伝われば、企業イメージの悪化は避けられません。一般消費者を顧客とする産業では、消費者の買い控えなどを通じて直接的な業績悪化につながるおそれもあります。また、取引先との関係性に影響が出たり、事業拡大の足かせとなったりするリスクも想定されます。さらに、人材雇用の場面でも、労働環境の質の低さが敬遠され、就職希望者が集まりにくくなる可能性があります。
過労死防止のために事業主が実施すべき取り組み
従業員の過労死を防止するためにも、事業主は長時間労働の削減や相談体制の整備などに取り組む必要があります。ここでは、事業主が実施すべき取り組みとして「長時間労働の削減」「組織風土の改革」「就業規則の見直し」「休息時間の確保」「相談しやすい環境の整備」の5点を解説します。
長時間労働の是正
過労死ライン超過を防ぐには、長時間労働の削減対策は欠かせません。勤怠管理システムやタイムレコーダーなどを用いた、従業員の労働時間を正確に把握する仕組みの導入は必須といえます。勤怠管理システムでは、長時間労働で働く従業員を把握するだけでなく、過労死ラインに到達しそうな場合に、従業員本人や上司にアラートを出して知らせるといった対策を講じることもできます。
長時間労働の是正については、以下の記事でより詳しく解説しています。
組織風土の改革
長時間労働を減らすためには、組織風土の改革が必要なケースも少なくありません。そもそも日本では、残業の多さが人事評価上プラスに働いていた側面があります。明示的な評価基準はなくても、長時間働く勤勉な従業員を上司が評価して、昇進・昇給において優遇しがちでした。長時間労働を減らすためには、残業をよしとする風潮を改めて、労働生産性や成果を評価しなければなりません。
また、決まった時間の朝礼や夕礼、多すぎる会議などが従業員の労働時間を延長する原因となる企業もみられます。このような非生産性的な企業文化を見直して、従業員が自分の作業に打ち込める状況にする必要があります。
就業規則の見直し
制度上、労働時間が過労死ラインに到達しないように、就業規則を見直すのもひとつの方法です。まず、就業規則における残業の上限規制が不十分な企業は、最優先で上限を規則に盛り込みましょう。就業規則を遵守して残業を課しているうちは、過労死ラインの到達や労働基準法違反が起こらない設計にするのです。残業を事前許可制にするといった制度導入も有効です。
休息時間の確保
終業から翌日の始業までの間に一定時間の休息時間を設ける、勤務間インターバル制度の導入も有効です。新たな過労死ラインの適用要件のもとでは、勤務と勤務のインターバルの短さが労災判断に影響をおよぼす可能性があります。一定のインターバルをとることを規定すれば、従業員は十分な休息を確保でき、心身の健康リスクの低減に役立つでしょう。
また、時間単位での有給休暇取得を可能にすると、柔軟に休暇を取りやすくなることから、従業員のリフレッシュに役立ちます。時間単位の年次有給休暇制度は、年5日の範囲内で従業員に1時間単位で有給休暇を取得させる制度です。制度の導入には労使協定の締結が必要です。
勤務間インターバルや時間単位の有給休暇などの取り組みの推進には勤怠管理システムが有効です。システム上で従業員の出退勤履歴を見て、従業員が勤務間インターバルをとれているかどうかが確認できます。また、多くの勤怠管理システムに有給休暇の申請や承認ができる機能が備わっています。
相談しやすい環境の整備
過労死や健康障害防止のためには、従業員が自身の不調に気付いたときに相談しやすい環境づくりと周知が重要です。
まずは、上司や同僚とコミュニケーションをとりやすい職場環境を築き、ストレスについて気軽に相談したり、サポートしたりできるようにしておくことが大切です。そのうえで、必要に応じて専門家の助言を活用しましょう。
専門家に相談するときは、国や民間団体によって設置されている健康相談窓口を利用するとよいでしょう。社内に相談窓口を設置するのも効果的です。社内に窓口を設置する場合、衛生管理者や産業医、人事スタッフなどと連携して、社内の課題やニーズに応じた相談体制を整えることが必要です。相談窓口の情報を従業員に周知することで、健康問題を抱える従業員に対して、同僚や上司など周囲の人間から相談を促してもらうことも期待できます。
また、従業員に自身の健康を意識させる方法として、ストレスチェックがあります。ストレスチェックは、従業員数が50人を超える企業で年に一度の実施が義務付けられている制度です。なお、50人未満の職場でも、日本では2027年までに50%以上の事業場でストレスチェックを実施することを目標としています。組織の規模にかかわらず、可能な限り導入が望ましい制度といえるでしょう。
ストレスチェックの結果が高ストレスであった場合、従業員は医師の面接を受けて助言を受けられます。ストレスチェックの実施に加え、実施結果の集団分析を行うことで負担のかかっている部署を把握でき、過重労働防止の対策を立てることができます。従業員自身も、ストレスチェックや面談を通じて、ストレス状況の把握やストレスを緩和する対策を講じることが可能です。
過労による健康への影響
過労は、しばしば脳や心臓、血管系の疾患の原因となります。また、ストレスにより精神疾患を引き起こすケースも少なくありません。長時間労働を原因とした疾患の例として、以下が挙げられます。
- 高血圧性脳症
- 脳内出血(脳出血)
- くも膜下出血
- 脳梗塞
- 心筋梗塞
- 狭心症
- 心停止
- 心臓性突然死
- 解離性大動脈瘤
- 精神疾患
- うつ病
生命の危機に直結しかねない重大な疾患が多くみられます。企業の経営者・管理者は、従業員が過労死ラインに到達するほどの過重労働を強いられることのないよう、労務管理を徹底しなければなりません。
まとめ
過労死ラインは、従業員が心身の健康悪化、死亡などの被害を負ったときに労災認定の判断基準となるものです。ただし、2021年の改正によって、長時間労働の基準に到達していなくとも、労働環境や条件によっては労災認定される仕組みとなりました。自社の従業員が過重労働により健康障害を負い、労災認定されるケースが多発すれば、労働基準法への違反による罰則だけでなく、企業イメージの悪化など経営面に大きなダメージとなる可能性もあります。企業の経営者・管理者は、従業員が心身ともに健やかに働けるよう、企業文化や制度を整備して、過労の発生を予防しなければなりません。
労務リスクを予防する第一歩は適切な勤怠管理から!
従業員の意図せぬ過重労働や休暇不足を予防するためには、適切で正確な勤怠管理を行うことが重要です。アマノの「TimePro-VG」を導入すれば、手間や負担をかけずに正確な勤怠管理が実現します。残業が多い、有給休暇取得の少ない従業員にアラートを出して、意図せぬかたちで起こる過重労働を予防することも可能です。勤怠管理が自動化されるため、管理者や労務管理担当者の負担を軽減できます。
-

業務改善ガイド 2021.07.02
-

業務改善ガイド 2021.07.29
-

業務改善ガイド 2021.07.02