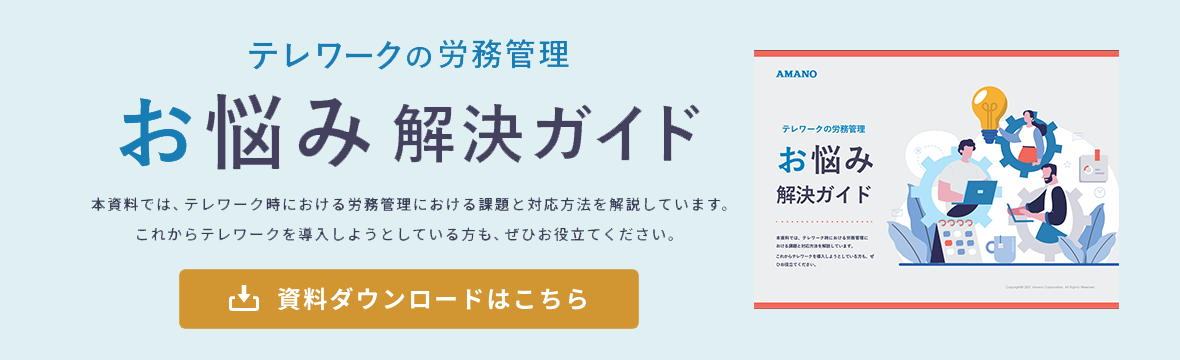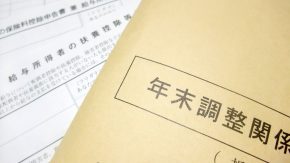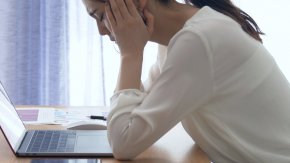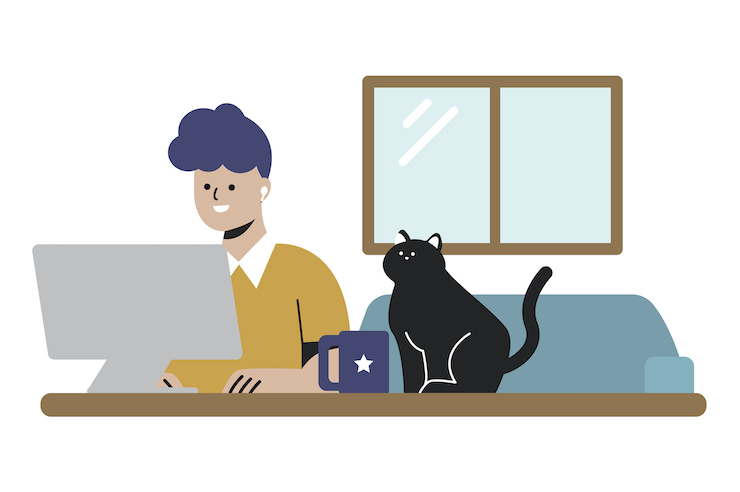
テレワークにおいても通常の勤務と同様に労働基準法関係法令が適用されるため、従業員の労務管理を正しく行えるように適切な措置を講じる必要があります。
この記事では、テレワーク下の労務管理でよくある課題や、課題解決に有効な労務管理システムについて紹介します。テレワーク下の労務管理にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
テレワーク時の労務管理については以下の資料もご覧ください。
隠れ残業の防止策やワーク・ライフ・バランスを保持する方法などよくあるお悩みと解決策を分かりやすくまとめています。
【資料ダウンロード】 テレワークお悩み解決ガイド
テレワーク下の労務管理ガイドライン
厚生労働省が「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を示しています。テレワーク環境で働いている場合でも、労働基準法は遵守しなければなりません。同ガイドラインに沿って労働環境を整備することで、テレワーク下の労務管理を適切に行えるでしょう。
例えば、次のような項目を遵守することが重要です。
- 労働条件の明示
- 労働時間制度の適用と留意点
- 休憩時間の取扱いについて
- 時間外・休日労働の労働時間管理について
テレワーク下の労務管理でよくある課題
テレワークでは従業員の行動を把握しにくく、どこでどのように業務を遂行しているかを管理者が確認することも困難です。その結果、次のような課題がしばしば発生します。
勤怠状況を把握しにくい
オフィスにいるときのように出退社や働きぶりを直接確認できないため、従業員の勤怠状況を把握しにくくなります。テレワークでは家事や些細な用事で中抜け(一時的に仕事から離れること)を希望する従業員も多く、中抜け時間の把握もしばしば課題となります。
テレワーク時の費用・手当負担が明確ではない
テレワークに使用する場所の光熱費や家賃、パソコンやスマートフォンなどの設備にかかるコストの負担が不明瞭になりがちです。
テレワーク時の作業環境や健康管理が難しい
自宅のパソコンを業務に使用する場合、パソコンの性能が低く、作業効率が下がる場合があります。また、勤務時間中・時間外の概念があいまいになり、生活が不規則になり健康状態に影響が出るリスクもあるでしょう。
労災認定の判断が難しい
オフィスに出社していないため、テレワーク中に発生した事故が業務時間中に発生したものなのかの判断が難しくなる場合があります。
人事評価が難しい
対面で仕事をしていないことで勤務態度や実際の作業品質などを把握しにくくなり、公平な人事評価が課題となる場合があります。
セキュリティリスク
外部から企業のシステムにアクセスするため、ネットワークが脆弱な場合、サーバー攻撃を受けたり、情報流出が発生したりするリスクがあります。
課題を放置していると、意図せず労働基準法の定めから逸脱する、従業員の心身の健康を損ねるといった問題につながるおそれがあります。そのため、こうした課題を把握して適切な労務管理方法を検討していかなければいけません。
テレワークにおける労務管理を適切に行うポイント
労働基準法をはじめとした諸法令を守り、また、従業員が快適に働ける環境を整備するためには、適切な労務管理が欠かせません。テレワーク下の労務管理におけるポイントを押さえておきましょう。
適切な勤怠管理の実施
始業・終業の時間を明確にして、適正に管理することが大切です。例えば、メールや電話での確認、勤怠管理システムの導入などにより、オフィス以外で働く従業員の勤務時間を把握できる体制を整えましょう。残業を完全事前申告制にするといった仕組みも有効です。
業務時間外のメール・チャットへの対応を余儀なくされ、勤務時間と生活時間が混同してしまう課題もあります。コミュニケーションツールの使用を業務時間内のみとするといった対策も有効です。
また、管理者はタスク管理をより厳格に行って、部下のタスク量を均一化するように努める必要があります。タスク管理ツールなどの導入も検討しましょう。
テレワークに即した就業ルールや規則を設定
テレワークに即した就業ルールや規則を設定することが大切です。勤怠報告の方法やコミュニケーションルールを設定します。
テレワーク下では、家の事情や通院などの私用で、休憩時間以外で一時的に業務から離れる「中抜け」に対応しやすくなると考えられます。中抜けに対しては就業時間を調整したり、有給休暇を時間単位で割り当てるなど、中抜け時間を勤怠管理に正確に加味できるようにルールを定めておくとよいでしょう。
また、自宅およびオフィス以外での業務の可否や、旅行や出張など移動中の業務に対する取り決めも必要です。
ツール導入により管理やコミュニケーションを円滑化
以下のようなITツールを導入することで、労務管理やコミュニケーションが円滑化します。必要なツールを積極的に導入して、正確かつ効率的な労務管理を実現しましょう。
- コミュニケーションツール
- タスク管理・プロジェクト管理ツール
- 労務管理ツール
テレワーク下の労務管理の課題にはツール導入が有効
テレワーク下の労務管理における課題解決には、ツール導入が有効です。特に、勤怠管理ツールと労務管理ツールの導入により、テレワーク下でも労働基準法などの各法令を守りつつ、従業員や管理部門がストレスを感じることなく労務管理を行うことが可能です。
勤怠管理システムで従業員の勤務状況を正確に管理
勤怠管理とは、出退勤時間や休憩時間、時間外労働時間、有給休暇の取得状況など、従業員の労働における数字的な記録を管理することです。
勤怠管理システムの導入により、管理者はテレワーク下でも従業員の勤怠状況を把握し、的確に管理できるようになります。長時間労働の予防にも役立つでしょう。また、勤怠打刻がしやすいツールを選べば、従業員の日々の勤怠報告の手間を軽減できます。
労務管理システムで従業員の労働環境や状況を管理
労務管理とは従業員の労働条件や労働環境を管理することです。
労務管理システムの導入により、入退社手続きや給与管理、社会保険、年末調整、マイナンバー管理など多様な人事業務が管理できます。テレワーク下における人事管理のさまざまな手続きを簡略化できるでしょう。
労務管理システムと勤怠管理システムを組み合わせて活用することで、テレワーク下の人事・労務業務を包括的に管理でき、効率化を図ることができます。
最適な労務管理ツールの選び方
労務管理に最適なツールの選ぶうえでは、次のようなポイントを重視して、自社に合ったツールを選定しましょう。
業務範囲に対応する機能を備えているか
労務管理全体をシステム化するなら、多機能なツールを選ぶのがよいでしょう。一方で、一部の業務ですでに導入が進んでいる場合は、給与管理、勤怠管理など求めている機能に特化したシステムの導入が有効な場合もあります。
費用対効果が適正か
基本的に、規模の小さい組織には、機能がシンプルで低コストのシステムが有効です。一方で、大企業のように規模の大きな組織の場合は、少々コストをかけてでも、データ処理能力が高く多機能なシステムのほうが、高い導入効果が期待できる場合があります。
ほかのツールやシステムと連携が可能か
すでにシステムを導入している場合は、既存システムとの連携が欠かせません。また、将来のシステム変更の余地を残すうえでは、幅広いシステムとの連携が可能なツールの選択が望ましいといえます。
電子申請に対応しているか
税務や社会保険などの電子申請に対応しているツールであれば、業務効率化に役立ちます。
サポート体制は充実しているか
導入前後にとまどったり、不慣れな従業員が申請や手続きを進められなかったりするおそれもあります。電話やメール、ときには訪問などによるサポートを柔軟に行っているツールを選ぶとよいでしょう。
まとめ
テレワークは働き方の多様性に応える効果的な仕組みですが、勤怠管理やコミュニケーション不足など、労務上の課題も多いです。労務管理システムと勤怠管理システムを併せてを活用すれば、法令を守りながら効率的な人事管理が実現するでしょう。
テレワークの労務課題を解決する多彩な機能
場所を選ばず打刻ができる勤怠管理システムです。残業時間超過を防ぐアラート機能やテレワークに合わせた各種設定にも対応し、労務リスクを未然に防止します。
-

業務改善ガイド 2021.07.02
-

業務改善ガイド 2021.01.27
-

業務改善ガイド 2022.02.18