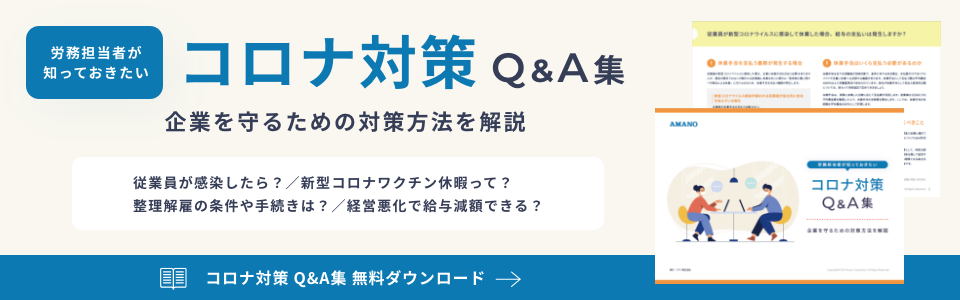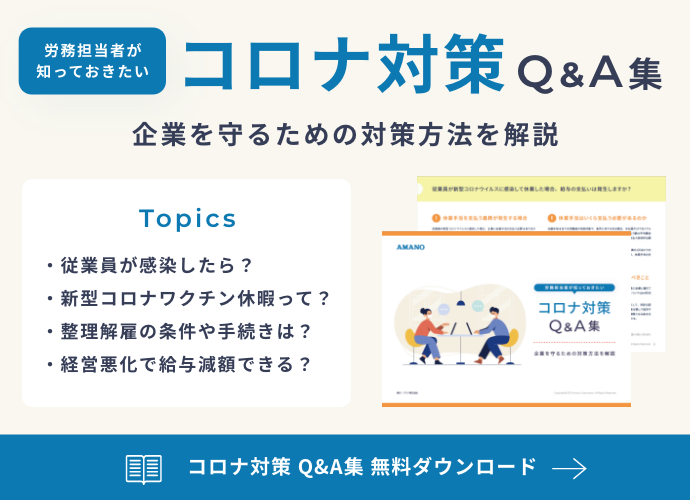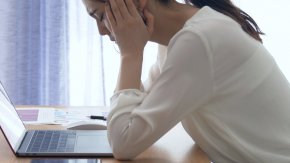オフィスでの感染予防対策
オフィスにおける感染症対策は、経団連の「オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」や日本産業衛生学会の「オフィス業務における新型コロナウイルス感染予防・対策マニュアル」に網羅的にまとまっており、このガイドラインに沿って進めることが求められます。詳細は各ページをご覧ください。
ここでは、オフィス内での基本的な飛沫・接触感染対策の方法と人の出入り時の感染対策を強化する方法について解説します。
【課題①】オフィスにおける具体的な飛沫・接触感染対策を知りたい
新型コロナウイルスは、一般的に飛沫感染・接触感染により感染します。特に室内での近距離の会話や不特定多数の人が共同で利用する場所などで感染リスクが高まります。飛沫感染と接触感染とは具体的に以下のような感染経路による感染を指します。
飛沫・接触感染とは?
飛沫感染:感染者のくしゃみや咳などの飛沫と一緒にウイルスが空気中に放出されます。そのウイルスを口や鼻から吸い込むことで感染します。
接触感染:感染者がくしゃみや咳を押さえた手で机やボタンなどに触れるとウイルスがつきます。他の人がその部分に触れると手にウイルスが付着し、口や鼻を触ることで粘膜から感染します。
企業には、オフィス内での感染対策の徹底が社会全体の感染拡大防止につながることを理解した上で、従業員の安全に配慮し、時差出勤やテレワークの導入、オフィス環境の整備などの感染対策の実施が求められます。特にオフィス内は人が集まり、出入りも多い場所なので感染対策の徹底が必要です。オフィス内における具体的な飛沫・接触感染対策として以下の取り組みが挙げられます。
| 飛沫感染対策 | |
| 業務スペース | 仕切りのない対面の人員・座席配置は避け、可能な限り対角に配置する |
| 顔の正面からできる限り2メートルを目安に、一定の距離を保つ | |
| 定期的な手洗いを徹底する | |
| 従業員に対し常時マスク着用に努めるよう徹底する | |
| 建物全体や個別の作業スペースの換気に努める | |
| 休憩・喫煙室 | 顔の正面からできる限り2メートルを目安に、一定の距離を保つ |
| 一定数以上の人が同時に利用しないように工夫する | |
| 休憩スペース、喫煙室の閉鎖を感染状況によって検討する | |
| トイレ | 共通で使用するタオルを禁止する |
| ペーパータオルを設置するか、従業員にタオルを持参してもらう | |
| トイレの蓋を閉めてから流すよう注意喚起する | |
| 接触感染対策 | |
| 共用部分 | 定期的な手洗いを徹底するよう従業員に通達する |
| ドアノブ、机などは定期的に消毒する | |
| その他共用設備については、頻繁に洗浄・消毒する | |
【課題②】入室時の感染対策を強化する方法を知りたい
オフィス内では上記で紹介したような感染症対策に加え、従業員の出退勤時や来訪者の入退館時にも感染対策の実施が求められます。
紙のタイムカードで出退勤の記録を残して勤怠管理をしている場合、複数の従業員がタイムレコーダーの機械に直接触れるため、接触感染の可能性が高まります。また、打刻するために複数の従業員が集まると、密になりやすく、飛沫感染のリスクも生じます。
顔認証やカードをかざすタイプのタイムレコーダーの導入は、非接触で出退勤記録を残せるため接触感染対策として有効です。また紙タイプと違い、従業員が自身のタイムカードを探す手間が省けるため、タイムレコーダーの周りに人が集まるのを防ぐ効果も期待できます。顔認証による出退勤を記録するタイムレコーダーの中には、検温機能を搭載しているタイプもあり、入室前の健康チェックが可能です。コロナ感染の疑いのある従業員の入室を防ぎ、社内での感染リスクを軽減できます。
来訪者向けの感染対策としては、カードによる非接触の入退室管理システムを用いて記録を残すことが重要です。ドアノブに触れずに済むため接触感染対策になります。さらに、ログを残しておけば、社内で感染者が出たときに来訪者に感染の疑いがあるかどうかを入退室のログを活用して調べることが可能です。
製造現場や店舗施設で取り入れたい感染対策
製造現場や店舗などの施設内では、接触感染対策として設備を消毒して回る手間やコストがかかる上に、人の出入りが激しくウイルスが空気中を舞い、感染が広がりやすい状態が発生します。
1章で紹介したような基本的な施設内の感染対策や入退室時の感染対策では対応しきれない課題と課題解決のポイント、必要なサービスについて解説します。
【課題①】施設内の除菌に手間やコストがかかる
製造現場や店舗施設では、施設内の除菌に手間やコストがかかる課題があります。基本的な感染対策として、アルコールによる物品や設備の消毒、除菌の実施が毎日必要です。しかし、広い施設の場合、消毒のために大量のアルコールが必要になり、毎月高いコストが発生する上、従業員の手指が荒れる原因にもなります。
アルコールよりもコストが低く消毒や除菌が可能なことから注目されているのが次亜塩素酸ナトリウムです。ただし、漂白や希釈(溶液に水などの溶媒を加えて濃度を薄くすること)濃度が不安定で、使用できる濃度にするのに手間がかかるという課題もあります。
これらの課題を解決できるのが、次亜塩素酸水の生成装置の導入です。アルコールでは1リットル1000円のところを、次亜塩素酸水なら1リットル約1円のコストしかかかりません。また、次亜塩素酸ナトリウムよりも低コストです。
さらに、次亜塩素酸ナトリウムは希釈に手間がかかりますが、次亜塩素酸水なら生成装置ですぐ利用可能な除菌用の濃度の溶液を作れます。このように、次亜塩素酸水の生成装置を導入すると、コストを抑えつつ、消毒にかかる手間の解消が期待できます。
消毒・除菌用アルコールの代替として次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は混同されがちですが、異なる物質である点に留意する必要があります。3種類の比較は以下表のとおりです。
| アルコール、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムの比較 | |||
|---|---|---|---|
| 次亜塩素酸水とアルカリ電解水で生成した電解水 | アルコール | 次亜塩素酸ナトリウム | |
| コスト | 約1円/リットル | 約1,000円/リットル | 約4円/リットル |
| 希釈の必要性 | 希釈不要 | 希釈不要 | 希釈が必要 |
| 速乾性 | 拭き取りが必要 | 不要 | 拭き取りが必要 |
| 安全性 | 食品添加物認定済み | 皮膚の油分を奪うため手が荒れやすい | 有害物質を含む |
【課題②】人の出入りが激しい施設内での感染リスクを下げたい
スーパーやショッピングモールなど人の出入りが多い場所や、衛生面での対策が必要な工場や病院などの施設には、感染リスクを下げる対策の徹底が必要です。しかし、人の手による清掃では時間、コスト的に限界があり、清掃時の除菌効果も不十分であるという課題があります。
ロボット床面洗浄機や手動式洗浄機を導入すると、人が歩くことで飛散しやすい床面のウイルスを除去できるため、施設内でウイルスが広がる可能性を軽減できます。床面洗浄機は、人の手でモップ清掃をした場合よりも床に付着した新型コロナウイルスを除去できます。また、コロナ対策のために清掃員を増員することなく、広範囲で精度の高い清掃が実施可能です。
| 人の手による清掃と床面洗浄機を導入した場合の違い | ||
|---|---|---|
| 人の手による床掃除 | 床面洗浄機による清掃 | |
| 作業量 | 1.水を床にまく 2.モップやデッキブラシで汚れをこする 3.ゴム製ワイパーなどで水を集めて取り除く |
1~3の作業を機械ですべて行う |
| 新型コロナウイルスの除去効果 | 不十分 | 98%以上減(Pタイル床) |
新型コロナウイルスは密閉された空間で感染しやすいことが分かっており、定期的な換気が必須なものの、冬場の気温が低い日に頻繁にオフィスで換気をするのは難しいという課題があります。
新型コロナウイルスの大きさである0.1μmの微粒子を捕集できる空気洗浄機を導入すると、実行性のある飛沫感染対策が可能になります。
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(2020年3月9日および3月19日公表)によれば、以下の3つの条件が重なった際に集団感染が発生しやすいことが分かっています。
- 換気の悪い密閉空間
- 多くの人が密集していた
- 近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われた
上記を踏まえ、厚生労働省は「空気清浄機の定量的なウイルス低減効果の評価については、さらなるデータの蓄積が必要であるが、HEPAフィルタ方式の空気清浄機に、空気中のウイルスを低減させる効果があることは明らかである」とまとめています。また、HEPAフィルタ方式の空気清浄機が有効とする根拠として、米国環境庁(USEPA)が示した「HEPAフィルタを備えているもの、または、粒径1μm 以下の粒子のほとんどを取り除くことができることを製造者が示しているもの」という選定基準を紹介しています。
新型コロナウイルスの感染対策として有効な空気清浄機の条件と使い方
- HEPAフィルタ付きであり、かつ、風量が 5m3/min 程度以上である空気清浄機を使用すること
- 0.1μmの微粒子を捕集できる空気洗浄機を使用すること
- 人の居場所から 10m2程度の範囲内に空気清浄機を設置すること
- 空気のよどみを発生させないように、外気取り入れの風向きと空気清浄機の風向きを一致させる
まとめ
在宅勤務の推奨や感染対策に関する社内の体制構築の他に、企業ではオフィスでの接触、飛沫感染対策を徹底する必要があります。人の出入りが多い小売の店舗や工場、病院などの施設、特に衛生管理を徹底させる必要がある場所では、自社の従業員の努力だけでは感染防止対策に対応しきれないため、感染防止措置の効率化と徹底が見込めるサービの導入がおすすめです。
入室時の感染対策強化には非接触のタイムレコーダーや入退室管理システム、消毒・除菌を低コストかつ効率的に行うための「次亜塩素酸水生成装置」のレンタルサービス、感染リスクをより低減させるには、自動清掃機、ウイルスを捕集できる空気洗浄機の導入が有効です。中大規模施設において、コロナウイルス感染症対策には自社のみで行うには限界があります。従業員および顧客の健康と安全を守るため、効率的かつ確実に感染症対策を行うサービスを取り入れることも検討してみてください。
関連記事
-

業務改善ガイド 2021.08.31
-

業務改善ガイド 2021.01.27
-

業務改善ガイド 2021.07.02