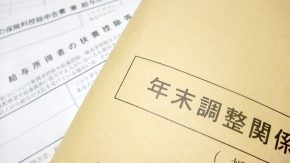本記事では、人事担当者が押さえるべき養育両立支援休暇の制度概要から実務運用まで、制度の特徴と具体的な導入手順を包括的に解説します。
改正育児・介護休業法の詳細については、以下の記事をご覧ください。
【社労士監修】2025年施行!改正育児・介護休業法のポイントや企業の対応策を解説
「柔軟な働き方を実現するための措置」への対応
改正育児・介護休業法により、すべての企業に新たな義務が課されます。企業は複数の選択肢のなかから自社に最適な組み合わせを判断し、効果的な両立支援体制を構築することが求められます。それぞれの特徴を理解して自社に最適な組み合わせを判断することが重要です。
5つの選択肢と企業の選択基準
企業は下記の選択肢から2つ以上を選択する必要があります。業務形態や従業員のニーズ、導入コストを総合的に勘案した戦略的な選択が重要です。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク
- 保育施設の設置運営
- 養育両立支援休暇の付与
- 短時間勤務制度
企業規模別の検討ポイント
企業規模により最適な制度の組み合わせは大きく異なります。自社の特性に応じた戦略的な選択により、投資対効果を最大化することが重要です。
中小企業(従業員数300人以下)の場合
限られたリソースのなかで効果的な両立支援を実現する必要があります。設備投資や大幅なシステム変更を伴わない選択肢(養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度、始業時刻等の変更)が現実的な選択肢です。人事担当者が少ない環境では、管理負担が軽くシンプルな制度設計が適しています。
中堅企業(従業員数300~1000人)の場合
複数拠点や多様な職種を抱える企業では、統一的な制度運用と柔軟性の両立が課題です。テレワーク導入が可能な部門もあれば、現場作業中心の部門もあるため、異なる業務特性に対応できる制度の組み合わせが必要です。
大企業(従業員数1000人以上)の場合
全国展開企業では制度の統一性が重要な検討項目となります。IT環境が整備されている場合はテレワークや始業時刻変更も現実的な選択肢です。同時に、製造現場や店舗など多様な職場環境を考慮し、全従業員が公平に利用できる制度の組み合わせを検討することが求められます。
養育両立支援休暇の概要
養育両立支援休暇は5つの選択肢のなかでも導入コストが低く、業務への影響を抑えながら従業員の両立支援ができる制度として注目されています。特に設備投資や大幅な業務変更を伴わずに導入できるため、多くの企業で有力な選択肢として検討されています。
対象者と取得可能日数の基本的な枠組み
養育両立支援休暇の対象となるのは、3歳から小学校就学前の子を養育する従業員です。この年齢設定は、子の看護等休暇や育児目的休暇とは異なる独自の対象範囲として設定されており、保育園から小学校への移行期における育児負担に配慮した制度設計となっています。
企業は年間10日以上の休暇を付与する必要がありますが、上限は企業が独自に設定することが可能です。管理期間については法律上の明確な規定はありませんが、実務上は4月1日から翌年3月31日の年度ベースでの運用が推奨されています。保育園や学校の年度との整合性を図ることができ、従業員にとってもより使いやすい制度となります。
時間単位取得の柔軟性と取得理由の範囲
養育両立支援休暇の大きな特徴は、原則として時間単位での取得を可能とする点です。従業員は保育園のお迎えや子どもの急な体調変化への対応など、育児のさまざまな場面で柔軟に休暇を活用できます。1日単位での取得に限定される従来の休暇制度と比較して、より実用性の高い制度として設計されています。
取得理由については、育児に関することであれば具体的な事由は従業員にゆだねられています。保育園の送迎、小学校の学校見学、子育て関連の手続きなど、幅広い用途での利用が想定されており、子の看護等休暇のように病気やケガに限定されない柔軟性があります。そのため従業員は日常的な育児のさまざまな場面で休暇を活用でき、仕事と育児の両立がより円滑になります。
労使協定と制度設計上の留意点
時間単位での取得を可能とする場合、企業は労使協定で取得可能な時間の範囲や申請手続きを明確に定める必要があります。労使協定では、最小取得単位(半日・1時間単位など)や1日の上限時間などを規定し、制度の適切な運用を図ることが重要です。また、申請の締切や承認フローについても、業務に支障をきたさない範囲で従業員の利便性を考慮した設計が求められます。
類似する育児関連休暇との違いと使い分け
2025年の法改正により、企業が管理すべき育児関連の休暇制度は複数存在することになります。従業員への説明時には制度運用上の混乱を防ぐため、養育両立支援休暇とほかの育児関連休暇の特徴と違いを明確に整理することが重要です。
3つの育児関連休暇の比較
| 制度名 | 対象年齢 | 付与日数 | 取得理由 | 法的位置づけ |
| 養育両立支援休暇 | 3歳〜小学校就学前年 | 年10日以上 | 育児に関することであれば柔軟 | 選択的義務(5つから2つ選択) |
| 子の看護等休暇 | 小学校第3学年まで | 年5日(2人以上は10日) | 病気・ケガ、予防接種、学級閉鎖等に限定 | 法定義務 |
| 育児目的休暇 | 小学校就学前 | 企業が設定 | 企業が設定 | 努力義務 |
実務での使い分けと運用上の注意点
子の看護等休暇との使い分けでは、対象年齢が一部重複するため、従業員が適切に使い分けできるよう明確な運用ルールの整備が必要です。子の看護等休暇は緊急時や医療関連の対応に特化し、養育両立支援休暇は日常的な育児の調整に活用するという役割分担を明確にしましょう。
育児目的休暇との統合・併用については、すでに育児目的休暇を導入している企業では養育両立支援休暇との重複を避け、従業員にとってより利用しやすい体系を構築する必要があります。制度の統合や役割分担を検討し、複雑化を防ぐことが求められます。
なお、これらの育児関連休暇はいずれも年次有給休暇とは別の制度として設計する必要があります。従業員が育児関連の休暇を積極的に活用することで、有給休暇の消化促進効果も期待できるでしょう。
養育両立支援休暇の導入メリットと企業への効果
養育両立支援休暇が5つの選択肢のなかでも多くの企業に注目される理由は、制度導入時の実用性と効果の高さにあります。限られたリソースで最大限の効果を得られる制度として評価されており、人事戦略の観点からも重要な選択肢として位置づけられています。設備投資や大幅な業務変更を伴わずに導入できる点が最大の魅力で、既存の勤怠管理システムに休暇種別を追加するだけで対応可能な場合が多いため、導入へのハードルが低いのです。
企業側のメリット
- 導入コストの低さ:設備投資不要で既存システムでの対応が可能
- 業務への影響の少なさ:時間単位での柔軟な取得により計画的な業務調整が実現
- 管理の簡便性:既存の休暇管理フローを活用した統一的な制度運用
- 法令遵守の確実性:明確な制度要件により適切なコンプライアンス体制を構築
従業員側のメリット
- 育児対応の柔軟性:保育園への迎えや学校行事など日常的な育児調整に活用可能
- 仕事と育児の両立:時間単位取得によりキャリア継続と育児の両立が容易
- 精神的負担の軽減:専用休暇の確保による安心感と時間的余裕の向上
- 有給休暇の有効活用:育児以外の目的での有給休暇利用が可能
長期的な組織運営への効果
養育両立支援休暇の導入は短期的な法令遵守だけでなく、中長期的な組織運営にも大きな効果をもたらします。子育て世代の従業員にとって働きやすい環境を整備することで、優秀な人材の定着率向上が期待できます。特に専門性の高い職種では、育児を理由とした離職を防ぐことで組織の知識継承にも貢献します。
人材採用面でも、仕事と育児の両立支援制度の充実は企業の魅力度向上につながり、求職者が企業選択をする際の重要な判断材料となるでしょう。優秀な人材の獲得競争で有利な立場を確保でき、従業員エンゲージメントの向上や全体的な生産性向上も期待できます。
実務運用の準備と導入手順
制度導入をスムーズに進めるためには、法的要件を満たすだけでなく、自社の実情に応じた制度設計と段階的な導入プロセスが重要です。計画的なアプローチにより、制度導入時の混乱を最小限に抑え、従業員にとって使いやすい制度として定着させることが可能です。
制度設計における主要検討事項
制度設計の第一歩として、以下の重要項目について自社の実情を踏まえた検討が必要です。
- 付与日数の決定:年間10日以上の範囲で自社の人員体制や業務特性に応じて設定
- 時間単位取得の運用方法:最小取得単位や1日の上限時間を決定
- 取得理由の範囲設定:育児関連の具体的利用場面を整理し従業員向け説明資料に反映
- 申請・承認フローの設計:既存の有給休暇申請フローを参考にした効率的な仕組みを構築
必要な手続きと書類整備
- 就業規則の改定:対象者、付与日数、取得手続き、時間単位取得の取り扱いを明記
- 労使協定の締結:時間単位取得の対象者、取得可能時間数、申請手続きを具体的に規定
- 運用マニュアルの作成:従業員向けと管理職向けの両方を整備し制度の適切な活用を促進
制度導入時は就業規則への明記が必須です。既存の育児関連休暇との関係性も整理して、従業員が理解しやすい条文構成とする必要があります。時間単位取得を可能とする場合の労使協定では、労働組合がある企業では組合との協議を、ない企業では従業員代表との協議を通じて適切な協定内容を検討することが重要です。
システム対応と効率的な管理体制の構築
勤怠管理システムでの対応は制度の円滑な運用には欠かせません。新たな休暇種別の追加、時間単位取得への対応、年間取得日数の管理機能など、システム側での設定変更や機能追加が必要です。申請・承認ワークフローの設計では、時間単位での申請に対応した入力画面や緊急時の取り扱いルール、承認者の設定などを適切に構築することで、運用開始後のトラブルを防止できます。
制度利用状況の管理・分析機能も重要な要素です。従業員別の取得状況や部門別の利用傾向を定期的に把握することで、制度の改善点や追加的な支援の必要性を見きわめることができます。
他社動向と導入の判断ポイント
制度選択で重要なのは、自社の状況に最も適した組み合わせを見きわめることです。同業他社の動向を参考にしつつ、自社の組織特性や従業員のニーズを踏まえた戦略的な判断が求められます。特に業種や企業規模により適切な選択肢は大きく異なるため、多角的な検証を通じて最適な制度設計を目指すことが重要です。
企業の選択傾向
企業の制度選択には、業種構造や組織規模、労働力構成などが影響します。例えば、労働集約型の中小企業では運用負担の軽さを重視する傾向が見られる一方、大規模企業や高度専門職を多く抱える組織では、柔軟な制度設計や人材定着策が評価されやすいと考えられます。また、地域の雇用慣行や業界特有のスキル要件も、制度採用の判断材料となります。
業種・規模別の適用性
業種や企業規模により、最適な制度の組み合わせは大きく異なります。以下は主要な業種・規模別の選択傾向と特徴です。
| 業種・規模 | 選択されやすい制度の組み合わせ | 選択理由・特徴 |
| 製造業 | 養育両立支援休暇 + 始業時刻等の変更 | 現場作業中心でテレワークの適用が困難、時間単位取得の柔軟性を評価 |
| サービス業(小売・飲食) | 養育両立支援休暇 + 短時間勤務制度 | 営業時間内の人員確保が重要、柔軟な人員配置を実現 |
| 金融・コンサル | テレワーク + 始業時刻等の変更 | 高度専門業務、場所にとらわれない働き方を重視 |
| 大企業(1000人以上) | 始業時刻等の変更 + テレワーク | 全国展開での統一運用、IT環境の整備状況を活用 |
| 中小企業(300人以下) | 養育両立支援休暇 + 短時間勤務制度 | 導入コストの低さと管理の簡便性を重視 |
導入判断のチェックポイント
自社にとって最適な制度選択を行うため、以下の観点から総合的な検討が必要です。
- 従業員構成の分析:3歳から小学校就学前の子を持つ従業員数と潜在的な利用者数の把握
- 既存制度との整合性:育児目的休暇や独自制度との重複・統合の検討
- 業務特性との適合性:職種別業務内容、繁忙期の状況、チーム体制との整合性評価
- 中長期的な人事戦略:企業の成長計画、人材確保戦略、働き方改革方針との整合性
最終的な意思決定では短期的な法令遵守だけでなく、投資対効果の高い両立支援体制の構築を目指し、従業員と企業双方にメリットをもたらす制度の組み合わせを選択することが重要です。
まとめ
養育両立支援休暇は、2025年10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」において、導入コストの低さと業務への影響の少なさから多くの企業が注目する実用的な選択肢です。
制度導入にあたっては、就業規則の改定や労使協定の締結、既存システムでの対応など、比較的簡便な手続きで実現可能である点が大きな魅力です。ほかの育児関連休暇との適切な使い分けを整理し、従業員が理解しやすい制度体系を構築すれば、法令遵守と人材確保・定着の両方を実現できる戦略的な制度として活用できます。
自社の業種や規模、従業員構成を踏まえた適切な制度選択をして、投資対効果の高い両立支援体制を構築し、持続可能な組織運営の基盤としていくことが重要です。
アマノの勤怠管理ソリューション
アマノでは、養育両立支援休暇をはじめとする多様な休暇制度に対応した勤怠管理システムを提供しています。法改正への迅速な対応と効率的な制度運用をサポートし、人事業務の負担軽減に貢献します。詳しい機能や導入事例については、以下のリンクからご確認ください。