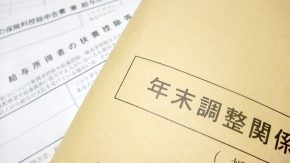井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
育児休業給付金の延長手続き
育児休業は原則的に子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得ができます。ただし、子どもが保育所等に入所できない場合は、育児休業を子どもが1歳6か月になる前日まで延長できます。さらに、1歳6か月になっても入所できない場合は、2歳の誕生日の前日まで再度延長が可能です。育児休業を延長する際は、雇用主に延長の申し出を行う必要があります。
育児休業期間を延長する場合は、育児休業給付金の延長手続きも必要です。保育所等の利用を申し込んだものの、すぐに入所できない場合は、市区町村が発行する「入所保留通知書」、「入所不承諾通知書」などの書類が必要となります。必要書類を育児休業給付金の支給申請書に添付して提出します。
入所保留通知書等だけでは不十分?
2025年4月からは 保育所等の利用申込書の写しと延長事由認定申告書の提出が必要となります。今回の変更までは入所保留通知書等の提出でよかったのですが、なぜ変更が必要になったのでしょうか?育児休業の延長が可能なのは保育所等に入所させることができない場合とされていますが、これはやむを得ない措置であり、本来は職場復帰することが原則です。
入所保留通知書は、希望した月(1歳の誕生月)に保育所が定員超過のため入所できないという結果だけを知らせるものです。そのため、この通知書だけでは、保育所への入所が本当にやむを得ず不可能であることを証明するのは難しいのが現状です。
例えば、自宅の近くに複数の保育所がある場合でも、定員超過している保育所だけに応募し、入所できないことを見越して申請するケースも考えられます。このようなことから、入所保留通知書等だけでは保育所等に入所させることができないと証明するには不十分と判断されたようです。
2025年4月以降の延長手続きのポイント
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更ルールが適用されるのは、子どもが1歳の誕生日を迎える前日、1歳6か月に達する日が2025年4月1日以降の被保険者が対象です。支給対象期間延長要件として次の3つをすべて満たす必要があります。
市区町村に保育利用の申込を行っていること(申込書の写しの提出が必要)
保育所への入所申込年月日は子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)までの日付になっている必要があります。入所申し込みを忘れていた場合は、延長は認められません。ここまでは従来どおりですが、改正後は申込書の写しの提出も必要となりました。
速やかな職場復帰のために保育所等の利用申込を行っていること(延長事由認定申告書の提出が必要)
育児休業および給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは制度の趣旨に反するとして、新たに要件が追加されました。
まず原則として、子どもの1歳の誕生日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていなければなりません。また、申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていない必要があります。合理的な理由とは、次のいずれかに該当する場合です。
(1) 申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合
(2) 自宅から30分未満で通える保育所等がない場合
(3) 自宅から30分未満で通える保育所等のすべてについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合
(4) 子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等はすべて申し込み不可となっている場合
(5) その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合
(6) 30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合
さらに、市区町村に対する保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないことも必要です。この意思表示については、入所申込書に「保育所等への入所を希望していない」「速やかに職場復帰する意思がない」などの記載がある場合は、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないとみなされます。
子供の1歳の誕生日時点で保育所利用のできる見込みがないこと(入所保留通知書等の提出が必要)
子どもの1歳の誕生日時点で保育が実施されないことを証明するため、従来どおり入所保留通知書等の提出が必要です。入所保留通知書等の発行年月日は子どもの誕生日の2か月前の日以後の日付となっている必要があります。
また、やむを得ない理由なく内定辞退をしている場合はこの要件を満たしません。やむを得ない理由とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所などの変更があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合です。
まとめ
2025年4月の改正により、育児休業給付金の延長手続きはこれまでより厳格になりました。一方で、新たに「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」などの制度も創設されています。これにより、育児と仕事の両立を支援する制度は、より手厚くなっています。制度を持続的なものとするためにも、公正公平な制度利用が求められます。
参考: