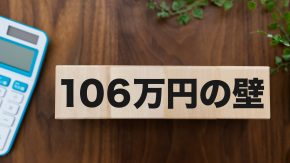働き方改革が推進されるなか、さらに長時間労働の改善に向けた法改正が行われる予定です。改正案の内容について解説します。

井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、現在は社会保険労務士として給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
勤務間インターバル制度とは?
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する制度のことです。2018年に成立した働き方改革関連法で、時間外労働の上限規制等の労働基準法の改正が行われましたが、同時に労働時間等設定改善法の改正が行われ、2019年4月より勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。
インターバル時間について定めはありませんが、11時間が望ましい水準、9時間が最低限確保してほしい水準とされています。EU加盟国がすべての労働者に24時間ごとに最低でも連続11時間のインターバル時間を確保するために必要な措置を設けていることが根拠となっています。
11時間の勤務間インターバル制度 義務化に向けた検討
現在、勤務間インターバル制度を導入している企業の割合は6%に過ぎないことから、労働基準関係法制研究会では諸外国の勤務間インターバル制度の内容を踏まえながら、導入の促進と法規制の強化について抜本的な検討が必要だとしています。
勤務間インターバル時間は基本的に11時間と設定されますが、例外もあります。インターバルが取れなかった場合の代替措置や11時間未満のケースも考慮されます。最終的な全面施行に向けて、段階的に実効性を高めることが望ましいとしています。
つながらない権利の検討
研究会では、インターバル時間に関連する「つながらない権利」についても検討されました。「つながらない権利」とは、勤務時間外や休日に仕事上のメールや電話の対応を拒否する権利のことです。
フランスではつながらない権利が法制化されていて、企業ごとに労使協議で許容範囲を決めています。勤務時間外にどのような連絡であれば許容範囲なのか、社内ルール策定のために労使の話し合いを促進するしくみを検討する必要があると提言しています。
休日の見直し
既存の制度では週1回の休日付与が原則ですが、実態として長期の連続勤務が発生し労災につながるケースも出ています。そこで、連続勤務の上限規制や法定休日の明確化など、より実効性のある休日制度への見直しが検討されています。
13日を超える連続勤務の禁止
現行制度では、毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を与えること、変形休日制の場合は4週間を通じて4日以上の休日(法定休日)を与えることが法律で定められています。しかし、業務の繁忙や業種・職種の特性により長期間の連続勤務を余儀なくされるケースもあり、労災事例も発生しています。
2週間以上の連続勤務が労災の認定基準となっていることから、36 協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13 日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けることを提案しています。
法定休日の特定
法定休日について、現在は前述した1週間に1日、または4週間に4日というルールしかなく、事前に法定休日を特定する必要はありません。改正案では、労働者の健康を確保するためにはあらかじめ法定休日を特定すべきであるとしており、罰則適用、法定休日の振替え、パートタイム・シフト労働者の休日をいつまでに特定するかなどを明確に定める必要があるとしています。
副業・兼業の場合の割増賃金の見直し
現行制度では、労働者が副業・兼業を行う場合、健康管理と割増賃金計算の双方で、労働時間を通算しなければなりません。本業・副業双方の使用者が、本業・副業先の労働時間を1日単位で細かく管理しなければならないことから負担が重く、雇用型の副業・兼業の許可や受け入れが困難になっています。
そこで、労働時間の通算は維持しながらも、割増賃金については通算を不要とする制度改正が必要だとしています。
労働時間の見直し
長時間労働是正の観点から、特例措置の実態に合わせた見直しや、管理監督者の健康確保に向けた新たな措置の導入など、より実効性の高い労働時間制度への改革が進められています。
法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
10人未満の飲食店や理美容業などは特例措置対象事業場として、1週間の法定労働時間が週44時間とされています。しかし、特例措置に該当する事業場の8割がこの特例措置を利用していないことから、業種による状況の違いを踏まえながら特例措置の撤廃を検討するとしています。
管理監督者等の健康・福祉確保措置
現行制度では、管理監督者等は長時間労働を行う場合でも特別な健康・福祉確保措置は設けられていません。
健康・福祉確保措置とは、労働時間が一定時間を超えた労働者に対し実施する項目で、特別条項付き36協定に記載が必要です。具体的には、医師による面接指導を実施する、終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保するなどがあります。管理監督者などにも健康・福祉確保措置を設けるとともに、管理監督者等の再定義を行う必要があるとしています。
まとめ
2019年4月から労働時間の上限規制、60時間を超える時間外労働の割増率5割以上、年5日の有給休暇取得の義務化などの労働基準法改正が行われました。しかし、長時間労働の防止策としては不十分な部分や、現行の働き方と過去に定められた制度が乖離している部分などが残っています。労使双方にとって利用しやすい制度改正が必要です。企業はこれを機に働き方を見直して、生産性向上を行っていくことが求められます。