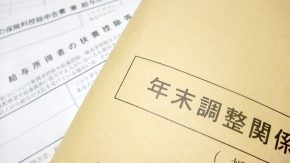井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
現状の問題点
複数の職場で働く場合の労働時間管理
現状では、使用者は労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合には、労働時間を通算して管理することが必要であると定められています。ただし、労働時間の通算が必要となるのは、「労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合のみです。副業が個人事業や業務委託の場合は法定労働時間にはあたらないため、通算する必要はありません。
使用者が労働時間を把握・管理するためには、労働者側から他事業主のもとでの労働時間について申告してもらう必要があります。副業・兼業を認めるかどうかは、事業主の判断にゆだねられています。しかし、職業選択の自由があるため、副業・兼業の禁止に法的拘束力はありません。実際には事業主に申告せずに副業・兼業を行うケースも多いのが実情です。
法定時間超過時の割増賃金負担
使用者は自らの事業場の労働時間制度を基に労働時間を通算する必要があります。自らの事業場の労働時間と、労働者の申告により把握した他事業場の労働時間を合計します。通算の結果、1週40時間、1日8時間を超える法定外労働に該当する場合があれば、36協定による労働時間の延長や割増賃金の支払いが必要です。
労働時間の通算方法は原則として、所定労働時間は先に契約をしたほうから順に通算します。所定外労働時間は実際に所定外労働が行われる順に通算します。
労働時間通算の具体例
| 項目 | 使用者A(先契約・先労働) | 使用者B(後契約・後労働) | 合計 |
| 所定労働時間 | 3時間 | 3時間 | 6時間 |
| 所定外労働時間 | 3時間 | 2時間 | 5時間 |
| 1日の労働時間合計 | 6時間 | 5時間 | 11時間 |
| 法定外労働時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 |
| 必要な対応 | 36協定の締結・届出 割増賃金の支払い | 36協定の締結・届出 割増賃金の支払い | - |
この例では、1日の労働時間の合計が11時間となり、法定外労働が3時間発生します。使用者Aでの所定外労働1時間と使用者Bでの所定外労働2時間の合計3時間が法定外労働となります。したがって、使用者AとBはそれぞれ36協定の締結、届出、割増賃金の支払いを行う必要があります。
企業にとって重い管理負担
上記のように、原則的な労働時間の通算方法では、労働時間の管理・計算が煩雑になります。企業側の負担も大きいため、別の通算方式も用意されています。使用者A(先契約)と使用者B(後契約)のそれぞれに上限労働時間を設定する方法です。上限時間を超えない限り、他事業場での実労働時間の把握が不要な管理モデルです。ただし、この方法でも労働者からの申告が必要で、上限時間を守らなければならないという制約もあります。そのため、使用者側の負担があることには変わりがありません。
また、労働者の事情によって割増賃金が生じる場合があります。長時間労働による業務遂行力の低下や健康への影響などにも配慮が必要です。副業・兼業がもたらす使用者への負担は大きくなっており、副業・兼業について見て見ぬふりをして、しかるべき対応を行っていない事業主も存在します。このため、副業・兼業を認める事業主は増加しているものの、事業主に副業・兼業の申告を行う労働者の割合はほとんど増加していないという結果が調査で出ています。
労働時間法制の見直し案
割増賃金制度の見直し
厚生労働省の第200回労働政策審議会(労働条件分科会)の資料では、以下のような観点から労働時間は通算するが、割増賃金は対象外とすべきという提言がされています。
| 項目 | 現行制度 | 見直し案 |
| 労働時間の通算 | 必要 | 必要 |
| 割増賃金の支払い | 通算時間で判断し支払い | 対象外とする |
| 健康確保措置 | 労働時間管理と一体 | 賃金計算と分離して管理 |
| 企業負担 | 大きい | 軽減される |
この提言の根拠として、以下の3つの観点が挙げられています。
- ヨーロッパ諸国の半数以上の国で実労働時間の通算は行う仕組みとなっているものの、フランス、ドイツ、オランダ、イギリスなどでは、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の通算を行う仕組みとはなっていない。
- 副業・兼業が労働者の自発的な選択・判断で行われることから、時間外労働に対する労働者への補償や時間外労働の抑制は、労働時間を通算したうえで本業先と副業・兼業先の両使用者におよぶものではないと考えられる。
- 副業・兼業の場合に割増賃金の支払いにかかる労働時間の通算が必要であることが、企業が自社の労働者に副業・兼業を許可したり、副業・兼業を希望する他社の労働者を雇用したりすることを困難にしている。
労働者の健康確保対策
一方で、労働者は使用者の指揮命令下で働く者であり、使用者が異なる場合も労働者の健康確保は大前提です。労働者が副業・兼業を行う場合に、賃金計算上の労働時間管理と健康確保のための労働時間管理は分けるべきという提言もされています。特に長時間労働が生じている場合の本業先と副業・兼業先の使用者の責任関係や健康確保措置の在り方については整理すべき点が多くあるとしています。
また、同一使用者の命令で複数の異なる事業場で働くケースや、出向先と出向元で労働者が兼務して働くケースも考えられます。そのような場合に割増賃金規制を逃れることがないようにする仕組みづくりが必要だとも述べています。
まとめ
副業・兼業の労働時間制度について現状と課題を見てきました。副業・兼業は憲法の職業選択の自由に基づくものであるため、規制をかけることが難しい現状があります。また、使用者は他の使用者のもとでの労働には責任を負わないことや、1人の労働者が長時間働き続けることには限界があることも考慮する必要があります。
これらを総合的に考えると、現行制度のように労働時間の通算と割増賃金の支払いを厳格に義務付ける仕組みをすべての副業・兼業ケースに適用することは困難と考えられます。副業・兼業の課題については、労働時間制度の整備だけでは解決できません。働き方改革やITによる生産性向上、最低賃金の増加などと一体となって総合的に取り組む必要があります。
参考: