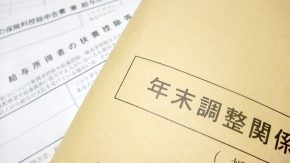改正育児・介護休業法については、育児関連に焦点が当てられがちですが、介護関連にも重要な改正があります。介護が必要な家族のいる労働者(以下、介護労働者)が仕事と介護を両立させるのは非常に困難です。介護には終わりが見えないという点で育児より苦しいともいえます。責任感の強い人ほど仕事を続けることをあきらめ、離職に至ることもあるでしょう。そのため、政府としてはこのような介護離職を防止するための法整備に力を入れています。

大友 大 氏
社会保険労務士
大手資格予備校にて、制作課チーフとして社労士試験必修テキストの執筆、全国模試の監修を行う。
平成20年より都内の社会保険労務士事務所に勤務ののち、平成26年に開業。
給与計算業務を中心に行いつつ、労務にまつわるさまざまな問題に取り組む。
大友労務管理事務所 代表
介護離職防止のための施策
2025年4月からの介護関連の改正は、「家族の介護を抱えている労働者が仕事と介護を両立できる社会の実現を目指して、仕事と介護の両立に当たっての課題や企業の両立支援策の状況を把握し、介護休業制度等の周知を行う等の対策を総合的に推進」とされており、具体的には次の4点となります。
- 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
- 介護離職防止のための雇用環境整備
- 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護のためのテレワーク導入
上記のうち、2点目、3点目は義務、「介護のためのテレワーク導入」は努力義務となります。
以下、それぞれの改正内容を説明します。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護労働者は会社への申し出により、有給休暇とは別に、介護を要する家族1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として介護休暇を取得できます。
ただし、労使協定によって除外された次の労働者からの申し出は使用者側が拒むことができるとされていました。
- 雇用継続期間6か月未満
- 1週間の所定労働日数が2日以下
このうち、「雇用継続期間6か月未満」を除外する規定が廃止されます。
| 改正内容 | 施行前 | 施行後 |
| 労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 | 〈除外できる労働者〉 1. 週の所定労働日数が2日以下 2. 継続雇用期間6か月未満 | 〈除外できる労働者〉 ・週の所定労働日数が2日以下 ※2.を撤廃 |
これにより、現在の就業規則、労使協定の一部改定が必要となります。
なお、日雇い労働者については労使協定の有無にかかわらず除外のままです。
介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるように、企業は次のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
これらの措置を少なくとも1つ以上講ずることが義務とされ、複数の措置を行うことが「望ましい」とされています。
また、雇用環境整備の措置については、現に介護に直面している労働者がいない場合や、当面そのような状況になりそうな方を採用する予定がなかったとしても講じる必要があります。
とりあえず1つ講じる、という場合であれば、4.の「周知」についてリンク先の厚生労働省HPの様式例を自社に合うよう修正して利用するのもよいでしょう。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
1. 介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
2022年4月から育児の方では妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、個別の周知・意向確認の措置が義務となっていますが、2025年4月から介護が必要となった労働者に対しても個別の周知・意向確認の措置が義務となります。
具体的には、介護に直面した旨の申し出をした労働者に対し、一定事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
周知事項
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部など)
- 介護休業給付金に関すること
個別周知・意向確認の方法
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等 のいずれか
厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイントのご案内」より抜粋
企業側は、労働者から申し出があった場合に対応できるよう、周知および意向確認の方法を定めておく必要があります。
方法として面談やメールなどが例示されていますが、書面に関しては厚生労働省で様式例が用意されています。自社に合うよう修正した様式を資料として用意し、面談で説明したうえで意向確認書を提出してもらうという手順で義務を果たすことができます。
2. 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で介護休業関連制度への理解と関心を深めるため、企業側から次に定める情報提供をする義務があります。
「早い段階」は40歳とされており、情報提供すべき期間は、労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度、または40歳に達した日の翌日(誕生日当日)から1年以内となります。
情報提供期間
- 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
- 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間
のいずれか
情報提供事項
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部など)
- 介護休業給付金に関すること
情報提供の方法
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等 のいずれか
厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法改正のポイントのご案内」より抜粋
この情報提供は、本人からの申し出があるないにかかわらず、使用者側から必ず発信しなければなりません。したがって、労働者の到達年齢を正確に把握しておくことが必要です。情報提供予定者のリストを作成し、時期が来たらすみやかに行う、と定めておくとよいでしょう。
社会保険の適用事業所であれば、ちょうど介護保険料の徴収開始時期と重なるため、該当者には同時に介護についての情報提供も行う方法も考えられます。
こちらも厚生労働省の様式例を活用するとよいでしょう。自社で一から作成する時間がない場合におすすめです。
介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に「努力義務」化されます。
制度内容については各企業で定めることとなっています。例えば、1か月につき何回まで、実施日を毎週固定の曜日とするなどの規定を就業規則に定め、労働者からの申し出によって利用可能とするようなイメージです。
自宅で介護を行う労働者にとっては、導入されれば非常に助かる制度です。しかし、テレワーク制度を廃止または縮小する企業も増えていることや、現実的に導入が可能な職種と不可能な職種があることから、当面は努力義務にとどまることが予想されます。
まとめ
仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま、介護離職する労働者が多くいます。今回の改正育児・介護休業法による個別周知や意向確認の義務化により、そのような人が救われ、企業も優秀な人材の流出を防ぐことができるかもしれません。
しかし、企業としては法の定めどおりに環境整備を行うことによる負担があるのも確かです。
特に、「労使協定による継続試用期間6か月未満除外規定」が廃止されたことは大きいでしょう。この改正により、(不本意ながら)採用に関しても慎重にならざるを得ない場面が出てくる可能性があります。
企業としては改正に柔軟に対応しつつ、国からの支援(両立支援等助成金等)も活用したうえで、労使ともに気持ちよく働けるような労働環境をつくるよういっそうの努力が必要です。