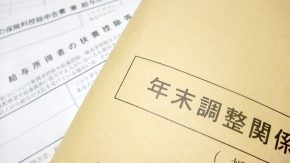井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
労災保険見直しの背景
労災保険法(労働者災害補償保険法)は、1947年(昭和22年)に制定されてから現在に至るまで、何度も改正が行われてきました。しかし、制度制定時に比べ社会や経済の環境は大きく変化しており、制度の前提条件そのものが適合しなくなっている可能性があります。そのため、保険料率や給付額等の数字上の改定ではなく、制度そのものの抜本的な見直しが必要という趣旨に基づき見直し案の検討が進められています。
遺族(補償)等年金の見直し
遺族(補償)等給付は労災保険法の1965年(昭和40年)の改正によって創設された制度です。労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失を補てんすることを目的としています。創設当時に比べ女性の雇用環境は大きく変わり、扶養家族の在り方も変化していることから、次の4つの論点で見直しが必要とされています。
遺族(補償)等年金の趣旨・目的をどう考えるのか
「被扶養利益の喪失」を補てんすることの妥当性とその範囲について、現在の社会実態を踏まえて検討すべきではないかと提案されています。
遺族(補償)等給付には、「遺族(補償)等年金」と「遺族(補償)等一時金」(給付基礎日額の1000日分)の2種類があります。 遺族(補償)等一時金は遺族(補償)等年金の受給資格を有する遺族が存在しない場合に、その他の遺族に支給されます。遺族(補償)等年金を受けられる範囲の遺族(受給資格者)は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者等の遺族です。ただし、遺族全員ではなく、そのうちの最先順位者(受給権者)だけが受けられるしくみになっています。
遺族(補償)等年金の支給期間には定めがなく、受給権者の範囲および順位については、労働者の死亡当時生計維持関係にあった者を基準としています。そのため、死亡時点だけでなく、将来にわたる扶養関係の変化も考慮した場合、どこまでが被扶養利益の喪失として補てんの対象となるべきかが問われています。
給付の要件について
「生計維持要件」と「夫と妻の要件の差」が論点のポイントです。現行では、遺族補償年金を受けられる遺族は労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとされています。生計維持要件の必要性について、要件の運用実績や社会実態の変化も踏まえ検討すべきではないかと提案されています。
また、現行では妻の受給権に要件がないのに対し、労働者たる妻の死亡時に55歳以上または一 定の障害の状態でなければ夫には受給権が生じません。さらに、妻については、55歳以上または一定の障害状態にある場合は、給付基礎日額が 153日分から175日分になる特別加算があります。女性の働き方が変化した現在、この差の妥当性について検討すべきと提案されています。
給付水準について
給付水準を見直すべきではないかと提案されています。現行の年金額は遺族(受給権者および受給権者と生計を同じくする受給資格者)の数等に応じて次のように決まります。
- 遺族数が1人の場合は給付基礎日額の153日分(遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
- 遺族数が2人の場合は給付基礎日額の201日分
- 遺族数が3人の場合は給付基礎日額の223日分
- 遺族数が4人以上の場合は給付基礎日額の245日分
現行の遺族(補償)等給付の金額の算定方法は1980年(昭和55年)改正時に採用されているものなので、現代に適合していない可能性があります。
労働基準法との関係について
現在の法解釈では、労災保険の給付状況にかかわらず、労災保険法に基づき保険給付が行われるべき場合、使用者は労働基準法による補償責任が免除されます。これについての検討が提案されています。
労災保険の遺族(補償)等一時金の給付額は給付基礎日額の1000日分ですが、労働基準法の遺族補償の給付額は平均賃金の1000日分です。また受給権者の順位が異なる場合があるので、両制度の差で不利益が生じないようにする必要性が問われています。
消滅時効の見直し
現行制度では、労働基準法における災害補償請求権および労災保険法の短期給付(療養補償給付、休業補償 給付、介護補償給付)の請求権の消滅時効は2年です。これについて見直しが必要ではないかとされています。一方、労災保険法の長期給付(遺族補償等給付、障害補償等給付)の請求権の消滅時効は5年です。
2020年(令和2年)の労働基準法の改正では、賃金請求権の消滅時効期間を5年間(当面は3年間)とする見直しが行われました。しかし、労働基準法による災害補償請求権および労災保険法の短期給付請求権の消滅時効期間は現状維持の2年間に据え置かれました。理由は、災害補償には早期解決の迅速性が求められるためとされています。しかし、近年は精神疾患などのメンタルヘルス案件が増加しているため早期の解決が困難であり、長期給付と同じ5年間の消滅時効期間が必要ではないかとされています。
まとめ
「労災保険制度の在り方に関する研究会」による労災保険制度の見直し検討会が現在進行中です。本記事の内容は第2回までの検討議案をまとめたものです。今後さらに見直し案が検討されていくことになるので、その行く末に注目したいところです。