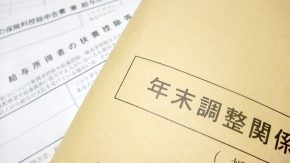本記事では、フリーランス新法とはどのような内容なのか、また、企業はどのように対応すればよいのかについて解説します。

井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
フリーランス新法とは
フリーランスとは
フリーランスとは一般的に、組織や団体などに所属せず、また雇用契約を結ばず、個人で仕事を請け負う働き方のことをいいます。フリーランスの代表的な職種としては、ライター、プログラマー、カメラマン、デザイナー、スタイリストなど専門的なスキルを生かして役務を提供する職種が挙げられます。また近年では、本業の勤務時間外に副業を始める労働者も増加しています。こうした副業者もフリーランスと呼ばれています。
ランサーズ株式会社が行った「【ランサーズ】新・フリーランス実態調査2021-2022年版」によると、2021年のフリーランス人口は1,577万人(労働人口の22.8%)でした。2019年の1,118万人(労働力人口の16.7%)から増加しています。
フリーランス新法ができた背景
フリーランスは企業との間で雇用契約を結ばないため、原則として労働基準法や雇用保険、社会保険などのセーフティネットが適用されません。しかし企業としては、従業員を雇用するよりフリーランスとして働いてもらう方が、人件費や固定費を抑えられることが多いです。そのため、なかにはフリーランスや業務委託の形態をとりながら、労働者と変わらない条件で働かせる例もあります。このような違法な雇用形態を偽装フリーランス(偽装請負)といいます。フリーランス人口の増加に伴って、偽装フリーランスの増加が予測されています。フリーランスが抱える取引上の問題やトラブルを解決するため、フリーランス新法が制定されました。
フリーランス新法の概要
フリーランス新法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、以下を目的としています。
- フリーランスと発注事業者の間の取引の適正化
- フリーランスの就業環境の整備
この法律の適用対象となる取引は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)となります。対象となるフリーランスは、従業員を使用しない個人または法人(役員が代表のみ)とされ、「特定受託事業者」と呼ばれます。一方、発注事業者はフリーランスに業務委託をする事業者が対象で、個人または法人を指します。そのうち従業員を使用するものを「特定業務委託事業者」、従業員を使用しないものを「業務委託事業者」と呼びます。
したがって、フリーランスがフリーランスに業務委託した場合の取引もこの法律の対象となります。ただし、フリーランスが商品を販売する取引は、業務委託ではなく単なる商品の販売行為であるため対象外となります。
フリーランス新法における発注事業者の義務と禁止行為
フリーランス新法の対象となるフリーランスは、契約形態は異なるものの、実質的には雇用労働者に近い立場にあります。そのため、この法律で発注事業者に課される義務は、労働法や労働契約法で雇用主に課される義務と多くの点で似通っています。
ただし、注意すべき点があります。形式上は業務委託契約を結んでいるフリーランスでも、実態として労働基準法上の「労働者」とみなされる場合があります。その場合は、労働基準関係法令が適用され、フリーランス新法は適用されません。
フリーランス新法で発注事業者に課せられた義務を解説します。
書面等による取引条件の明示義務
発注事業者がフリーランスに対し業務委託をした場合は、 ただちに取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。ただし、明示する書面の様式は定められていません。電磁的方法には、チャットやメールの本文に明示事項を記載する方法や、URLやPDFを添付する方法が認められています。
明示すべき項目は以下のとおりです。
- 発注事業者およびフリーランス(特定受託事業者)の名称
- 業務委託をした日
- フリーランスの業務の内容
- 給付を受領または役務の提供を受ける期日
- 給付を受領または役務の提供を受ける場所
- 報酬の額および支払期日
- 給付に検査が必要な場合はその期日
- 現金以外で報酬を支払う場合はその支払い方法
報酬支払期日の設定・ 期日内の報酬支払義務
特定業務委託事業者は、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の、できる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払わなければなりません。
禁止行為
特定業務委託事業者は、フリーランスに対し1カ月以上の業務委託をした場合は、以下7つの行為をとることが禁じられています。発注事業者とフリーランスとの間で合意があったとしても、以下の行為は法令違反となるため、十分に注意する必要があります。
1.受領拒否
フリーランスに責任がないにもかかわらず、納品物の受け取りを拒むこと
2.報酬の減額
フリーランスに責任がないにもかかわらず、業務委託時に定めた報酬額を後から減額すること
3.返品
フリーランスに責任がないにもかかわらず、納品物を受け取った後に引き取らせること
4.買いたたき
通常支払われる対価に比べ、著しく低い報酬額を設定すること
5.購入・利用強制
正当な理由なしに、発注事業者が指定するものを強制的に購入・利用させること
6.不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスの利益にならない金銭や労働力の提供をさせること
7.不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないにもかかわらず、発注を取り消したり、やり直しをさせること
募集情報の的確表示義務
特定業務委託事業者は、広告などによりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはなりません。正確かつ最新の内容に保つ必要があります。
育児や介護と業務の両立に対する配慮義務
特定業務委託事業者は、6カ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申し出に応じて必要な配慮をしなければなりません。
申し出の内容を十分に把握し、取り得る対応を十分に検討した結果、どうしても必要な配慮ができない場合には、配慮できない旨を伝達できます。ただし、その理由を書面の交付やメールの送付などの方法で、わかりやすく説明する必要があります。
ハラスメント対策に係る体制整備義務
特定業務委託事業者は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることのないよう、相談体制の整備といった措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を 行ったことなどを理由として、不利益な取扱いをしてはなりません。
中途解除等の事前予告・理由開示義務
特定業務委託事業者は、6カ月以上の業務委託について、途中で契約の解除や更新停止を決めた場合は、原則として30日前までに予告しなければなりません。(災害時のやむを得ない場合や、フリーランスの責めに帰すべき理由がある場合などは予告不要です。)また、予告した日から解除する日までに、フリーランスから解除理由の開示請求があった場合は、解除理由を開示しなければなりません。
フリーランス新法に違反した場合
発注事業者がフリーランス新法に違反した場合、フリーランスは行政機関に違反の事実を申し出ることができます。行政機関は、フリーランスの申し出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行います。発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行ったにもかかわらず、勧告に従わない場合は命令・公表がなされる可能性があります。命令違反には50万円以下の罰金も科せられます。
発注事業者は、フリーランスが行政機関へ申し出をしたことを理由に、契約の解除や今後の取引を中止するといった不利益な取扱いをしてはなりません。
企業がすべきこと
これまでフリーランスに発注してきた企業は、フリーランス新法の規定に基づき、その業務委託契約が適切なものかを再度確認することが大切です。場合によっては、業務委託契約を見直し、雇用契約に変更することも考えられるでしょう。一方で、業務委託契約を継続することが望ましい場合には、フリーランス新法に対応した書類や社内体制を整備する必要があります。
まとめ
IT技術の進化とそれに伴うワークスタイル、ライフスタイルの変化により、働き方の多様化が進み、正社員と非正社員、労働者とフリーランスの間の壁がなくなってきています。例えば、各種保険の適用範囲の拡大や、フリーランスの労災保険の特別加入など、個人のセーフティーネットは広がりつつあります。
労働人口が減少する現代では、企業にとって、経営資源に占める人的資源の価値はますます高まっているでしょう。企業は働き手が安心して十分に能力を発揮できるように、多様な働き方に対応できる環境と、社内の風土づくりを進めていくことが大切です。