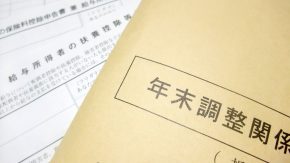人事・労務なんでもQ&A
営業成績が著しく悪く、メンタル不調で休業と復職を繰り返している従業員がいるのですが解雇できますか?

大友 大 氏
社会保険労務士
大手資格予備校にて、制作課チーフとして社労士試験必修テキストの執筆、全国模試の監修を行う。
平成20年より都内の社会保険労務士事務所に勤務ののち、平成26年に開業。
給与計算業務を中心に行いつつ、労務にまつわるさまざまな問題に取り組む。
大友労務管理事務所 代表
Q. 営業成績の悪化とメンタル不調を理由とした解雇は可能でしょうか
人事部で労務管理を担当しています。営業部に所属する中堅社員(入社8年目)が、この2年間で営業成績が著しく低下しており、目標達成率は30%程度にとどまっています。メンタル不調を理由に3か月の休職を2回繰り返しており、復職後も短期間で再び体調を崩すという状況が続いています。
会社としては営業成績の改善を求めていますが、本人は「プレッシャーが原因でメンタル不調になる」と主張しており、根本的な解決に至りません。他の営業担当者や売上への影響を考慮すると、解雇を検討せざるを得ない状況です。このような場合、法的に解雇することは可能でしょうか。
A.メンタル不調を伴う能力不足による解雇はきわめて困難です
メンタル不調による休業と復職を繰り返す従業員の解雇は、法的にきわめて困難な判断となります。労働契約法第16条により、解雇は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」ことが必要ですが、メンタル不調がかかわる場合はこの要件を満たすことが困難です。
営業成績の悪化が解雇理由となるためには、改善指導や配置転換などの措置を十分に講じたうえで、それでも改善が見込めないことを立証する必要があります。しかし、メンタル不調が原因の場合は会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があり、むしろ適切な支援を行うことが法的に求められます。次節以降で詳しく解説します。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
メンタル不調を伴う解雇の法的リスク
メンタル不調を理由とした解雇やメンタル不調者への不適切な対応は、重大な法的リスクを伴います。会社は従業員の精神的健康についても配慮する義務があり、これを怠った場合は損害賠償責任を負う可能性があるのです。
近年の裁判例では、メンタル不調の従業員に対する会社の対応がより厳しく問われる傾向にあります。適切な配慮を行わずに解雇した場合、不当解雇として多額の賠償金を命じられるケースも増加しています。
安全配慮義務の具体的内容
会社の安全配慮義務は単に事故防止対策だけでなく、従業員の精神的健康への配慮も含まれます。過度な業務負荷の軽減、適切な休息時間の確保、メンタルヘルス不調の兆候への早期対応などが具体的な義務として認められています。
営業成績の悪化がメンタル不調と関連している場合、成績向上のプレッシャーを与え続けることは安全配慮義務違反となる可能性があります。法的にはむしろ、適切な支援体制を構築することが求められるのです。
障害者差別解消法との関係
メンタル不調が精神障害に該当する場合、障害者差別解消法による保護を受ける可能性があります。この場合、合理的配慮の提供が義務づけられ、配慮を行わずに解雇することは差別的取扱いと判断される危険性があります。
診断書の有無にかかわらず、明らかにメンタル不調の症状が見られる従業員に対しては慎重な配慮が必要です。専門医の意見を求めながら、適切な支援策を検討することが重要です。
営業成績不振による解雇の要件と限界
営業成績の不振を理由とした解雇は、一般的に「能力不足解雇」として位置づけられます。しかし、この種の解雇は労働者保護の観点から厳格な要件が設けられており、簡単には認められません。
解雇が有効となるためには、具体的かつ継続的な指導を行い、改善の機会を十分に与えたうえで、それでも改善が見込めないことを客観的に立証する必要があります。メンタル不調がかかわる場合は、これらの要件を満たすことがさらに困難になります。
改善指導の実施と記録化
営業成績不振を理由とした解雇を検討する前に、具体的で実効性のある改善指導を継続的に実施する必要があります。目標設定の見直し、スキル研修の提供、上司による定期的なフォローなど、多角的な支援を行わなければなりません。
重要なのは、これらの指導内容を詳細に記録化することです。いつ、どのような指導を行い、従業員がどのような反応を示したかを記録した文書は、解雇の正当性を立証する根拠となります。
配置転換の検討義務
営業職での成績不振が続く場合でも、ただちに解雇することはできません。他部署への配置転換が可能かを検討し、従業員の能力を生かせる職務があれば異動を提案することが求められます。
ただし、メンタル不調がある場合の配置転換は症状の悪化を防ぐ観点から慎重に行う必要があります。産業医や主治医の意見を聞きながら、本人の意向も尊重した配置を検討しましょう。
適切な復職支援と継続的なサポート体制
メンタル不調による休職と復職を繰り返す従業員に対しては、解雇を検討する前に適切な復職支援体制を構築することが法的にも実務的にも重要です。段階的復職プログラムの導入や継続的なメンタルヘルスサポートにより、根本的な問題解決を図ることが求められます。
復職支援の充実は当該従業員の職場定着だけでなく、他の従業員のメンタルヘルス向上にも寄与します。組織全体の生産性向上と離職率の改善にもつながる投資として位置づけることが重要です。
段階的復職プログラムの設計
休職と復職を繰り返す従業員には、従来の復職プログラムの見直しが必要です。より緩やかな復職ステップの設定、柔軟な勤務時間制度の活用、業務負荷の段階的調整などを組み合わせた個別プログラムを作成しましょう。
営業職の場合は顧客対応から始めて徐々に営業活動に復帰させるなど、ストレス要因を段階的に増加させる工夫が有効です。無理な目標設定は避け、本人のペースに合わせた復職を支援することが重要です。
産業医との連携強化
メンタル不調を繰り返す従業員への対応は、産業医の専門的な判断が必要です。定期的な面談により、従業員の精神状態の変化を的確に把握し、適切な就業上の配慮を決定する必要があります。
産業医がいない企業でも外部の産業医サービスや精神科医との連携により、専門的なサポート体制を構築することが可能です。コストはかかりますが、解雇に伴うリスクを考えれば必要な投資といえるでしょう。
他の従業員への影響と組織マネジメント
成績不振とメンタル不調を抱える従業員への対応は、他の従業員のモチベーションや組織の士気にも大きな影響を与えます。公平性の確保と組織全体の生産性維持のバランスを取りながら、適切な組織マネジメントを行うことが重要です。
透明性のある対応方針を示し、他の従業員の理解と協力を得ることで組織全体のメンタルヘルス向上と生産性の維持の両立が可能になります。
公平性の確保と説明責任
一部の従業員に対する特別な配慮が他の従業員の不満や疑問を招かないよう、公平性の確保が重要です。メンタルヘルス支援制度の全社的な周知や、誰もが利用できる相談窓口の設置などにより、組織全体での取り組みであることを明確にしましょう。
ただし、個人の健康情報は機密事項であるため、具体的な症状や治療内容を他の従業員に開示するのは避けなければなりません。制度の説明と個人情報の保護を両立させる配慮が必要です。
チーム全体のパフォーマンス向上策
営業成績不振の従業員がいる場合、チーム全体のパフォーマンス向上策をあわせて実施することが効果的です。営業手法の見直し、顧客管理システムの改善、チーム内での知識共有の促進などにより、組織全体の底上げを図りましょう。
これらの取り組みは、成績不振の従業員にとってもスキル向上の機会となり、メンタル不調の改善にも寄与する可能性があります。個人への対応と組織全体の改善を連動させることが重要です。
解雇以外の選択肢と段階的対応
解雇を検討する前には、さまざまな選択肢を十分に検討することが法的にも求められます。配置転換、職務変更、勤務条件の調整、研修機会の提供など、多角的なアプローチにより問題解決を図ることが重要です。
これらの取り組みを段階的に実施し、その効果を客観的に評価することは、最終的に解雇が必要となった場合の正当性の担保にもつながります。
職務内容の見直しと調整
営業職での成績不振が続く場合は職務内容の見直しを検討しましょう。新規開拓営業から既存顧客のフォロー営業への変更、営業事務やマーケティング支援への一部業務転換など、本人の適性に合わせた調整が必要です。
メンタル不調がある場合は、ストレス要因となる業務の特定と軽減が重要です。ノルマのプレッシャーが主な要因であれば、目標設定の方法を変更したり、チーム営業制を導入したりすることで改善が期待できます。
勤務条件の柔軟な調整
時短勤務、フレックスタイム制などを活用して、従業員が働きやすい環境を整備しましょう。これらの制度は、会社の安全配慮義務の履行や解雇回避努力の一環として検討すべき措置といえます。
営業職の場合、内勤日と外勤日のバランス調整や、移動時間を考慮した柔軟なスケジュール設定により負担軽減が可能です。本人の体調や回復状況に応じて段階的に調整を行いましょう。
解雇を検討する場合の法的要件と手順
すべての支援策を講じても改善が見込めず、やむを得ず解雇を検討する場合は、厳格な法的要件と適正な手順を遵守する必要があります。労働契約法第16条の要件を満たし、解雇予告や解雇理由証明書の交付など、法定手続きを適切に履行することが不可欠です。
ただし、メンタル不調がかかわる解雇は特に慎重な判断が求められ、法的リスクが高いことを十分に認識しておく必要があります。
客観的合理的理由の立証
解雇が有効となるためには、営業成績不振が客観的で継続的なものであり、改善の見込みがないことを具体的に立証する必要があります。数値データ、指導記録、面談記録などを整備し、第三者が見ても納得できる根拠を準備しましょう。
メンタル不調がかかわる場合は、医学的見地からの判断も重要です。産業医の意見書や主治医の診断書を参考に、就労継続の可否について専門的な判断を求めることが必要です。
社会通念上の相当性の検討
解雇の社会通念上の相当性は、企業規模、従業員の勤続年数、過去の類似事例への対応、解雇による影響の程度などを総合的に勘案して判断されます。中堅企業で勤続8年の従業員を解雇する場合は、特に慎重な検討が必要です。
また、メンタル不調の従業員を解雇することが社会的にどう受け止められるかも重要な要素です。企業の社会的責任や評判への影響も考慮して判断する必要があります。
予防策と組織的な取り組み
メンタル不調による休職と復職の繰り返しを防ぐためには、予防的な取り組みが重要です。ストレス要因の早期発見と対処、働きやすい職場環境の整備、管理職のマネジメントスキル向上などにより、根本的な問題解決を図りましょう。
これらの取り組みは現在の問題だけでなく、将来的な類似問題の発生防止にもつながります。組織全体のメンタルヘルス向上と生産性の向上を同時に実現することが可能です。
ストレスチェック制度の活用
労働安全衛生法により義務づけられているストレスチェック制度を効果的に活用し、メンタル不調の早期発見と予防に努めましょう。結果を分析して職場のストレス要因を特定し、改善策を実施することが重要です。
営業部門では、ノルマによるプレッシャー、顧客対応のストレス、長時間労働などが主なリスク要因となります。これらを数値化し、継続的にモニタリングすることで、予防的な対応が可能です。
管理職研修の充実
メンタル不調の早期発見と適切な対応のためには、管理職のスキル向上が不可欠です。部下の変化に気づく観察力、適切な声かけの方法、専門機関への橋渡し役としての機能などを研修で習得させましょう。
特に営業部門の管理職は、売上目標の達成圧力と部下のメンタルヘルス配慮のバランスを取る難しい立場にあります。具体的な事例を用いた実践的な研修により、適切な管理手法を習得させることが重要です。
まとめ
営業成績不振とメンタル不調を理由とした解雇は法的に困難であり、リスクを伴います。まずは適切な復職支援と継続的なサポート体制の構築により、根本的な問題解決を図ることが重要です。
解雇を検討する場合も、段階的な支援措置を十分に講じたうえで厳格な法的要件を満たす必要があります。ただし、メンタル不調がかかわる場合は、解雇よりも支援に重点を置いた対応が法的にも実務的にも適切です。
組織全体のメンタルヘルス向上と生産性の維持を両立させるためには、予防的な取り組みと早期対応が不可欠です。勤怠管理システムを活用した働き方の可視化により、適切な労務管理を実現しましょう。
復職支援と労務管理にはアマノの勤怠管理ソリューション
アマノでは、メンタルヘルス不調者の復職支援にも活用できる勤怠管理システムをご用意しています。時短勤務や段階的復職にも柔軟に対応し、従業員の働き方を適切に管理できる機能が充実しています。労務リスクを軽減し、従業員の健康管理を強化したい企業の皆様は、以下のラインアップをご確認ください。