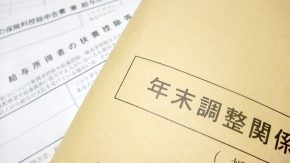今回の改正では、社会保険の加入対象の拡大による「106万円の壁」撤廃のほかにも、さまざまな制度の見直しが行われています。本記事では、社会保険の加入対象の拡大以外の改正内容について解説します。
「106万円の壁」については、以下の記事で詳しく解説しています。
【社労士監修】社会保険の106万円の壁撤廃が決定

井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
在職老齢年金の見直し
在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者の制度です。一定額以上の報酬がある場合、年金の支給が調整されます。今回の改正により、支給停止の基準額が引き上げられます。
在職老齢年金の支給停止基準の比較
| 項目 | 改正前(現行) | 改正後(2026年度~) |
| 支給停止基準額 | 月50万円 | 月62万円 |
| 支給停止額の計算 | 超過分の半額 | 超過分の半額 |
計算例:賃金45万円+厚生年金10万円の場合
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 合計額 | 55万円 | 55万円 |
| 基準額との差 | 5万円超過 | 7万円の余裕あり |
| 支給停止額 | 2.5万円 | 0円(停止なし) |
| 実際の受給額 | 7.5万円 | 10万円 |
上記計算例のように基準額の引き上げにより、多くの高齢者が年金の減額を受けずに働き続けることができるようになります。
平均寿命と健康寿命が延びるなか、働き続けたいと考える高齢者は増加しています。また、労働市場では人材確保や技能継承の観点から高齢者雇用のニーズも高まっています。実際に、65歳から69歳の就業率は2003年の34.7%から2023年は約52.0%(総務省「労働力調査」基本集計による)に大幅に伸びています。しかし、在職老齢年金の受給者308万人のうち16%(約50万人)が在職停止者となっています(厚生労働省および社会保険出版社による2022年度末の統計データ)。在職停止者とは、年金額の一部または全部が支給停止される人のことです。
さらに65歳から69歳の3割以上が、年金額が減らないように時間を調整して働いているという調査結果もあります(厚生労働省調査、2025年時点)。このような高齢者の働き控えによる雇用ロス等が課題となっていました。この課題を解決するため、2026年度からは厚生年金が支給停止となる基準額が大きく引き上げられる予定です。
遺族厚生年金の見直し
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者等が亡くなった場合に、一定の要件を満たしていれば遺族が受給できる年金です。現状では、遺族が女性か男性かによって受給の年齢要件が異なります。今回の改正で男女の受給年齢要件が共通化され、以下のようになります。
遺族厚生年金の受給要件の比較
| 性別・年齢 | 改正前 | 改正後 |
| 女性 30歳未満で死別 | 5年間有期給付 | 5年間有期給付※ |
| 女性 30歳以上で死別 | 無期給付 | 60歳未満で死別:5年間有期給付※ 60歳以上で死別:無期給付 |
| 男性 55歳未満で死別 | 給付なし | 5年間有期給付※ |
| 男性 55歳以上で死別 | 60歳から無期給付 | 60歳未満で死別:5年間有期給付※ 60歳以上で死別:無期給付 |
表のとおり、改正後は男女ともに60歳未満で死別した場合は原則5年間の有期給付となります。ただし、障害年金受給者や低所得者等で配慮が必要な場合は、5年目以降も給付が継続されます。
今回の改正の目的は、女性の就業進展や共働き世帯の増加を踏まえた男女差の解消です。そのため、現行では女性だけが対象の中高齢寡婦加算が廃止されます。代わりに、新たに有期給付に加算する有期給付加算が創設されます。
また、有期給付の継続は最長65歳までとなります。65歳からは老齢厚生年金に移行し、死亡分割という新しい仕組みも設けられます。死亡分割では亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割し、遺族の記録に上乗せします。
男女差解消以外にも、子どもを養育している遺族への経済的支援を強化する改正が行われます。具体的な内容は以下のとおりです。
子ども加算の増額
- 対象者:子どもを養育している遺族厚生年金受給者
- 対象となる子ども:18歳になった年度末まで(障害がある場合は20歳まで)
- 加算額:子ども1人につき年額281,700円
遺族厚生年金の改正は2028年4月から実施されますが、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定で、中高齢寡婦加算は2028年4月から25年かけて廃止に向けて段階的に縮小されることになっています。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
厚生年金の標準報酬月額の上限は現在65万円となっています。賃金が月65万円を超えても、保険料はそれ以上増えないしくみです。この65万円は、全被保険者の標準報酬月額平均の約2倍に相当します。
上限額を平均の約2倍に設定している理由は2つあります。ひとつは年金の給付額に大きな差が出ないようにするため、もうひとつは保険料の半分を負担する事業主の負担を考慮しているためです。
一方、年金を受け取る側から見ると問題があります。どんなに賃金が高くても年金額は増えることがありません。つまり、収入に応じた年金を受け取ることができないのです。
この問題を解決するため、新しい仕組みが設けられました。賃金が上昇傾向にあることから、今回の改正により標準報酬月額の上限を65万円から75万円に引き上げられます。引上げは2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に行われる予定です。標準報酬月額の上限が75万円になると、賃金が月75万円以上の人は現在と比較して保険料負担は月9,100円増加、年金額は10年該当とすると月約5,100円の増加となります。
私的年金の見直し
私的年金制度では、加入年齢の延長や拠出限度額の拡充など、老後資産形成を支援する改正が実施されます。iDeCo(個人型確定拠出年金)は個人が任意で加入する年金制度で、企業型DC(企業型確定拠出年金)は企業が導入する年金制度です。主な改正内容は以下のとおりです。
iDeCoの拠出限度額と加入年齢の改正(2025年6月成立法案)
| 区分 | 改正前 | 改正後(公布から3年以内に施行予定) |
| 加入年齢上限 | 65歳 | 70歳 |
| 第1号被保険者(自営業者等) | 月6.8万円 | 月7.5万円 |
| 第2号被保険者(企業年金等に加入していない会社員) | 月2.3万円 | 月6.2万円(企業型DC等の掛金がある場合はその分を差し引き) |
| 第2号被保険者(企業年金等に加入している会社員・公務員) | 月2.0万円 | 月6.2万円(企業型DC等の掛金がある場合はその分を差し引き) |
企業型DCの改正
- 拠出限度額:月5.5万円 → 6.2万円
- マッチング拠出の制限撤廃(加入者掛金が事業主掛金を超えることが可能)
上記の私的年金の改正は2025年6月から3年以内に実施される予定です。
まとめ
2025年6月成立の年金制度改革法では、「106万円の壁」撤廃に加え、在職老齢年金の支給停止基準の引き上げや遺族厚生年金の男女格差是正、私的年金(iDeCo・企業型DC)の加入年齢引き上げ・拠出限度額拡大など、幅広い制度改正が盛り込まれました。
これらの見直しは、高齢者の就業促進や多様な働き方・老後資産形成を後押しすることを目的としており、今後3年以内に段階的に実施される予定です。
参考: