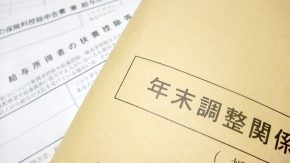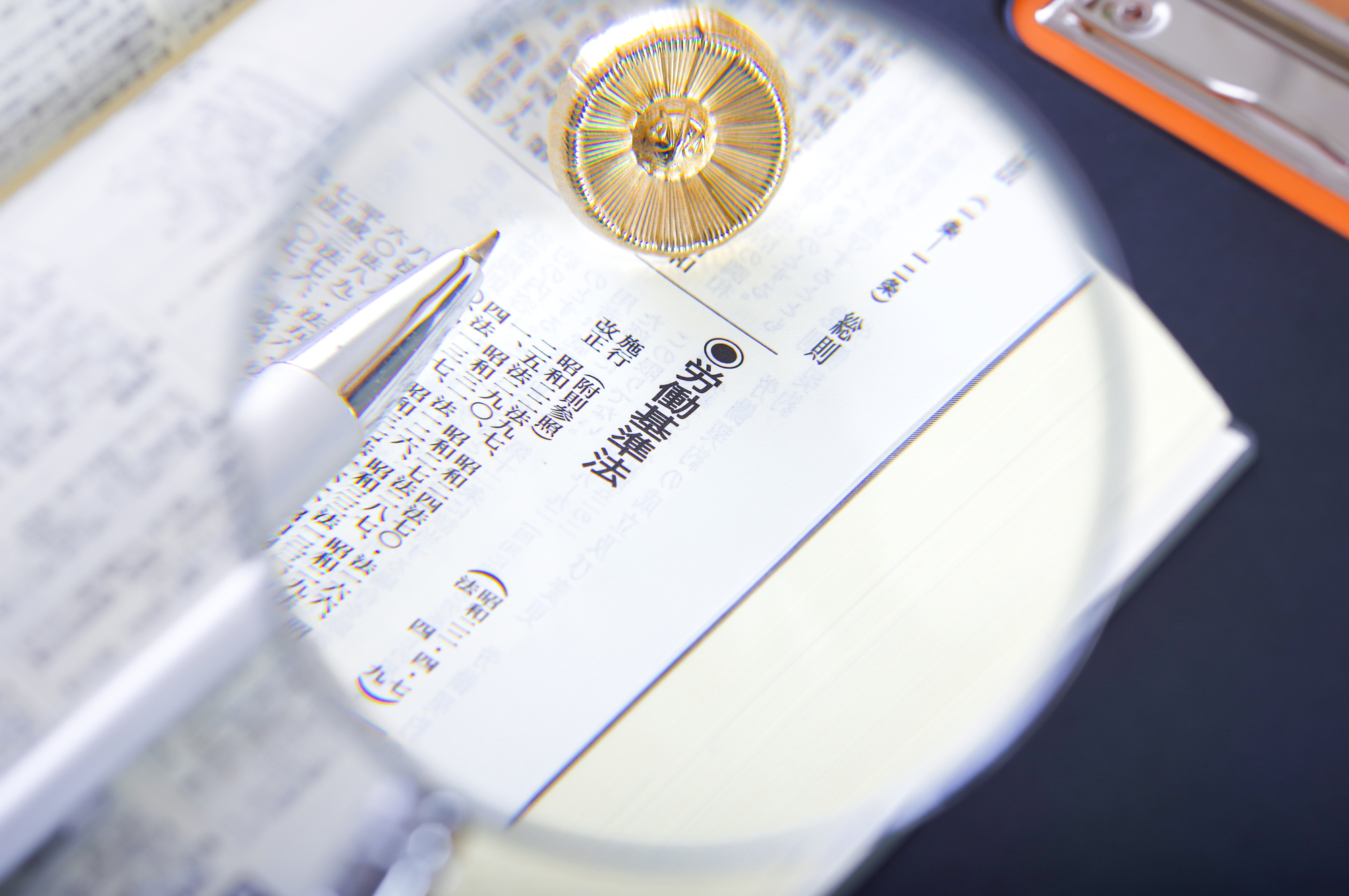
2025年1月に開催された第193回労働政策審議会労働条件分科会の資料「労働基準関係法制研究会報告書」の内容から、議論されている主な改正点を紹介します。

井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
見直しが必要とされている内容
労働政策審議会労働条件分科会で抜本的な見直し・改正が必要であるとして議論の対象になっているのは次の4つの分野です。各分野について、どのような課題があるのか見ていきます。
(1) 労働基準法の「労働者」の定義
(2) 労働基準法の「事業」の定義
(3) 労使コミュニケーションのあり方
(4) 労働時間法制
労働基準法の「労働者」の定義
労働基準法の保護の対象は「労働者」となっています。「労働者」とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。
しかし、雇用契約や労働契約とは異なる名称の契約のもとで働く人がいます。このような役務提供者は、実態として「労働者」と同じような働き方をしているにもかかわらず、労働基準法の「労働者」に該当するかどうかが課題になっています。
特にデジタル技術の進歩やリモートワークの広がりによって、フリーランスやプラットフォームワーカーという新しい働き方をする人が急激に増えています。
このような働き方をする人たちの労働者性をどのように判断し、労働基準法の保護の対象とすべきかが問われています。課題の解決策として、2024年には「フリーランス新法」や労災保険のフリーランスの特別加入制度が設けられました。
労働基準法の「事業」の定義
労働基準法の「事業」の概念は、事業場という場所を単位として基本的に成り立っています。したがって労働保険や就業規則、36協定の届出等は事業場ごとに行うことになっています。
しかし近年、テレワークの普及により働き方が多様化しています。このような状況下で、労働条件の設定に関する法制適用の単位が事業場単位を原則とし続けることの妥当性が問われているのです。
今後は、労務管理、意思決定、権限行使、義務履行がなされる場面や場所、監督の実効性を考慮する必要があります。そのうえで、事業場を単位とすべきか、企業単位とすることも許容されるかを検討すべきとされています。
基本的には事業場単位を原則として維持します。しかし、企業単位や複数事業場単位で同一の労働条件が定められている場合があります。このときに労使コミュニケーションが行われる場合は、労使の合意により手続を企業単位や複数事業場単位で行うことも選択肢に入れるべきとしています。
労使コミュニケーションのあり方
法律で定められた規制の原則的な水準は、労使の合意など一定の手続きを経ることで、個別の企業や事業場、労働者の実情に合わせて調整や代替が可能です。このための仕組みが労使協定です。労使協定は、事業場に過半数労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は過半数代表者と使用者が締結します。
労働組合の推定組織率は2023年(令和5年)では16.3%で長期的にも低下しており、過半数労働組合がない事業場が多いという実情があります。また、過半数代表者について、選出方法や労働者集団としての意見を伝える役割・能力などに課題があるという実情もあります。
このような状況において、労使間のコミュニケーションをより実質的、効果的なものとするため、次の4点について法的な整備を行っていく必要があるとされています。
(1) 過半数代表者の選出手続き
(2) 過半数代表、過半数労働組合、過半数代表者の担う役割および使用者による情報提供や便宜供与、権利保護
(3) 過半数代表として活動するに当たっての過半数代表者への行政機関等の相談支援
(4) 過半数代表者の人数や任期の在り方についての法的な整備
労働時間法制の見直し
労働時間法制の見直しについては、
(1) 最長労働時間規制について
(2) 労働からの解放に関する規制
(3) 割増賃金規制
の3つの分野での見直しが論議されています。各分野の具体的課題について見ていきましょう。
最長労働時間規制の見直し
最長労働時間規制については、次の5点についての見直しが検討されています。
1.時間外・休日労働時間の上限規制
自動車運転者や医師などは、2024年度から時間外・休日労働時間の上限規制が適用となりましたが、なお一般より長い上限が適用されています。そのため、健康確保措置のあり方や一般の上限規制の適用に向けた取り組みをどのようにするかを議論すべきとされています。
2.企業による労働時間の情報開示
労働環境の改善を促すためには、企業による自主的な情報開示が質・量ともにより充実するよう、その基盤を整えることや義務的な情報開示について検討すべきとされています。
3.テレワーク等の柔軟な働き方
テレワークにはフレックスタイム制などの柔軟な労働時間制度が活用されることが多く、実労働時間の管理が必要となります。仕事と家庭生活が混在し得るテレワークについては、実労働時間を問題としないみなし労働時間制の導入が求められます。
4.法定労働時間週44時間の特例措置
10人未満の飲食店や理美容業などは特例措置対象事業場として、1週間の法定労働時間が週44時間とされています。しかし、該当する事業場の8割がこの特例措置を利用していないことから特例措置は撤廃するべきとされています。
5.実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置
現行制度では管理監督者等は長時間労働を行う場合でも特別な健康・福祉確保措置は設けられていませんが、督者等にも健康・福祉確保措置を設けるとともに、管理監督者等の再定義を行う必要があるとされています。
労働からの解放に関する規制の見直し
労働からの解放に関する規制については、次の5点についての見直しが論議されています。
1.休憩
1日8時間を大幅に超えて長時間労働する場合も休憩は1時間でよいのか、逆に1日6時間以下の短時間労働の場合、従来どおり休憩なしでもよいのか検討する必要があるとされています。
2.休日
現行制度では、毎週少なくとも1回の休日(法定休日)を与えること、変形の場合は4週間を通じ4日以上の休日(法定休日)を与えることが最低条件となっています。しかし、長時間労働防止の観点から36協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」という規定を労働基準法上に設けることが必要ではないかとされています。
3.勤務間インターバル
勤務間インターバル時間として11時間を確保することを原則としつつ、制度の適用除外とする職種等の設定や、実際に11時間の勤務間インターバル時間が確保できなかった場合の代替措置等を設けるべきとされています。
4.つながらない権利
労働時間ではない時間に、使用者が労働者の生活に介入する権利はありませんが、突発的な状況への対応や顧客からの要求等によって、勤務時間外に対応を余儀なくされることがあります。その結果、私生活と業務との切り分けがあいまいになっているため、勤務時間外のつながらない権利の基準を明確にすべきとされています。
5.年次有給休暇
計画的・長期間の年次有給休暇を取得できるようにするための手法を検討し、年次有給休暇取得時の賃金の算定方法の見直しを行う必要があるとされています。
割増賃金規制の見直し
割増賃金規制についての見直しでは、次の2点についての見直しが論議されています。
1.割増賃金の趣旨・目的等
深夜労働の割増賃金について、使用者の命令ではなく、働く時間の選択に裁量のある労働者(管理監督者、裁量労働制適用労働者等)が自ら深夜帯に働くことを選んだ場合には、割増賃金は必ずしも求められないのではないか。
2.副業・兼業の場合の割増賃金
現行制度では、労働者が副業・兼業を行う場合、健康管理と割増賃金計算の双方で、労働時間を通算しなければならないため、雇用型の副業・兼業の許可や受け入れが困難になっている。国は副業・兼業を進めていることから、企業の副業・兼業の許可や受け入れの負担を軽くするため、労働時間の通算は維持しながらも、割増賃金については通算をしないようにするべき。
まとめ
労働政策審議会労働条件分科会での労働関係法令の見直し案について見てきました。これらのなかには早期に取り組むべきものと、中長期的な視点をもって取り組むべきものとがあります。しかし、遅かれ早かれ上記の見直し案が実行される可能性は高いため、企業は前もって準備していく必要があると考えられます。
参考: