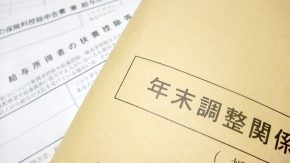井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
出生後休業支援給付金支給申請のポイント
出生後休業支援給付金とは
出生後休業支援給付金は共働き・共育てを推進するため新たに設けられた制度です。子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて支給されるため、給付金が上乗せされることになります。支給日数は最大28日間で、支給額は休業開始時賃金日額×休業日数×13%となっています。
出生後休業支援給付金の支給対象になるには、被保険者要件と被保険者の配偶者要件の2つの要件を満たす必要があります。被保険者の性別によって確認するポイントや支給申請の際に提出する添付書類等は異なります。被保険者が父親(男性)の場合と母親(女性)の場合に分けて、子が実子である場合の支給申請のポイントを説明します。
保険者が父親(男性)の場合の要件
被保険者が父親(男性)の場合、対象期間に出生時育児休業(産後パパ育休)を14日以上取得していることが被保険者要件です。対象期間は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間です。
被保険者の配偶者(母親)については、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが要件です。これは、子の出生日の翌日時点で、配偶者(母親)が産後休業中、無業者、雇用される労働者でない場合など7つの事由に該当することを指します。
産後パパ育休については、以下の記事で詳しく解説しています。
被保険者が女性の場合の要件
被保険者が母親(女性)の場合、対象期間に育児休業を14日以上取得していることが被保険者要件です。対象期間は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間です。
被保険者の配偶者(父親)については、対象期間に14日以上の育児休業を取得している、または子の出生日翌日に「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが要件です。対象期間は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間です。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」の具体例
配偶者(父親)の育児休業が不要とされるケースは、以下のような場合です。ただし、単に「仕事が忙しい」「会社の都合で休めない」といった業務上の理由で育児休業を取得しない場合は該当しません。
1.配偶者の就労状況による場合
- 無業者(働いていない)
- 自営業者やフリーランス(雇用される労働者ではない)
- 日雇い労働者で育児休業を取得できない
2.家庭状況による場合
- 配偶者がいない(単身)
- 配偶者と子に法律上の親子関係がない
- 配偶者からの暴力により別居中
3.制度上の理由による場合
- 育児休業を取得しても給付金が支給されない
- 育児休業給付の受給資格がない
- その他、制度上育児休業を取得することができない
支給申請手続きについて
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請とあわせて、同一の支給申請書を用いて行います。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能です。ただし、その場合は出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請しなければなりません。
支給申請の際には、被保険者の配偶者について、
(1) 「配偶者の被保険者番号」欄
(2)「配偶者の育児休業開始年日」欄
(3)「配偶者の状態」欄
のいずれか1つを記入します。被保険者が母親の場合は、配偶者(父親)に育児休業取得状況を確認する必要があるため、(1)から(3)のいずれか1つを記入することになります。被保険者が父親の場合は配偶者(母親)の育児休業取得要件は不要のため、(3)欄を記入することになります。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」の証明書類は、被保険者が母親の場合は該当する理由の違いによって証明書類が異なります。被保険者が父親の場合は、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)(いずれも写し可)を提出のみでよいとされています。
育児時短就業給付金申請のポイント
受給資格と資格要件
育児時短就業給付金は、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(育児時短就業)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。育児時短就業給付金の支給を受けるためには、まず大前提として、
(1) 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(一般被保険者または高齢被保険者)であること
(2) 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて育児時短就業を開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12か月あること
の要件を両方満たしている必要があります。
そのうえで、
(3) 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
(4) 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
(5) 初日から末日まで続けて、育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
(6) 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
の4つの要件を満たしている月が支給の対象です。
なお、支給対象となる時短就業とは、1週間あたりの所定労働時間を短縮する措置を取っていることを指します。フレックスタイム制の場合は清算期間における総労働時間を短縮していること、変形労働時間制の場合は対象期間の総労働時間を短縮していることが必要です。
短縮後の1週間あたりの所定労働時間に上限・下限はありません。ただし、短縮後の1週間あたりの所定労働時間が20時間を下回る場合は注意が必要です。この場合、子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが、就業規則等の書面により確認できる場合を除きます。これに該当しない場合は、雇用保険の被保険者資格を喪失することとなり、育児時短就業給付金の支給対象となりません。
月の途中で離職し、被保険者資格を喪失した場合は(3)の要件を満たさなくなるため、離職した月は対象となりません。また、週所定労働時間20時間未満の労働条件で転職した場合は、被保険者にならないため支給対象にはなりません。
支給対象期間
支給対象期間は、育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までで、各暦月(支給対象月)について支給されます。ただし、以下4つの日の属する月までが支給対象期間です。
(1) 育児時短就業にかかる子が2歳に達する日の前日
(2) 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
(3) 育児時短就業にかかる子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
(4) 子の死亡その他の事由により子を養育しないこととなった日
なお支給申請は、原則として2か月ごとに(2つの支給対象月について)行うこととなっていますが、1か月ごとに行うことも可能です。支給申請期限は支給対象月の初日から起算して4か月以内です。
支給額と支給率
原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されますが、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。また、
(1) 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
(2) 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
(3) 支給額が最低限度額以下であるとき
のいずれかの場合、給付金は支給されません。
なお、育児時短就業開始時の賃金を確認する書類として、初回申請の際には育児時短就業開始時賃金の届出が必要です。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。
参考: