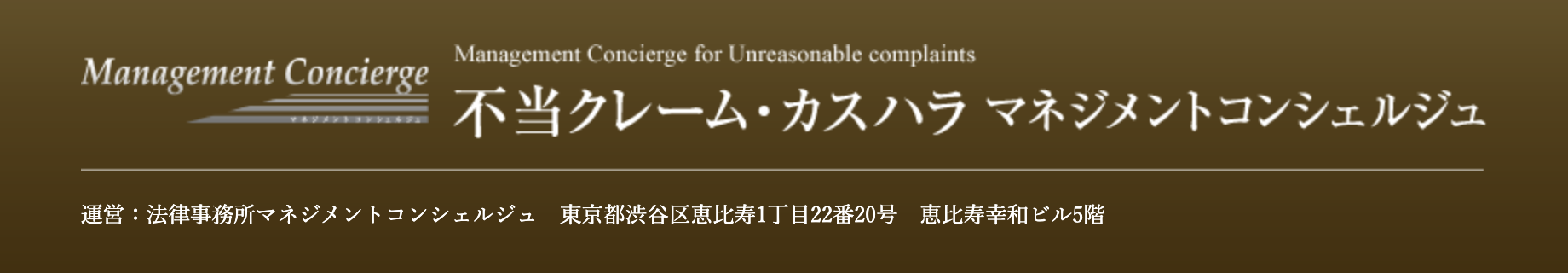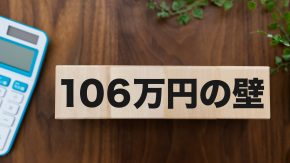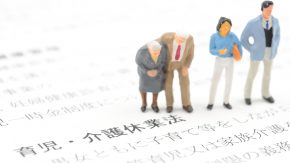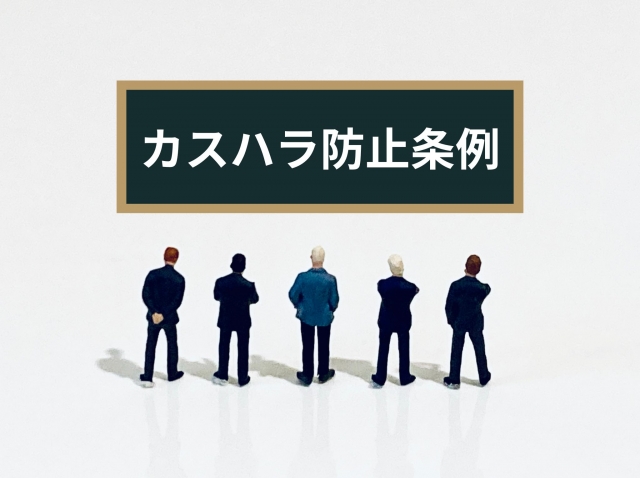
厚生労働省は、カスハラを単なるクレームとは異なる問題として捉え、その防止に向けた取り組みを推進しています。
本記事はカスハラ対策に実績がある、 「法律事務所マネジメントコンシェルジュ」に監修いただきました。
「法律事務所マネジメントコンシェルジュ」では、 カスハラ、不当クレームに関するご相談および幹部・従業員研修を実施しております。
「法律事務所マネジメントコンシェルジュ」へのご相談はこちら。
カスハラとは
厚生労働省によると、企業の現場において、以下のようなものがカスハラにあたると考えられています。
「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」
具体的には以下のようなものが例として挙げられています。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
- 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・模様が社会通念上不相当な言動」の例
要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 土下座の要求
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 従業員個人への攻撃、要求
要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
- 商品交換の要求
- 金銭補償の要求
- 謝罪の要求(土下座を除く)
顧客からの要求が正当な範囲を超え、従業員の心身に負担をかける場合、これを防ぐことは企業の義務であり、単に労働者保護だけでなく、企業の健全な運営のためにも重要です。
カスハラに関する裁判例
カスハラに関する裁判例は多くありますが、企業の安全配慮義務が問われた例についてご紹介します。
- 私立小学校の教師が、保護者からの理不尽な言動を受けたことに対し、校長が教師の言動を一方的に非難し、もっぱらその場を収めるため、その教師に対して、保護者に謝罪するよう求めたことが不法行為と判断。小学校を設置するA市および教員の給与を支払うB県に損害賠償の責任を認めた。(甲府地裁 平成30年11月13日判決)
カスハラの対応には時間を要し、精神的にも大きな負担を感じることが少なくありませんが、安易にその場を収めようとして、何も非がない労働者に会社が謝罪をさせたりする行為は慎むべきです。これは、小学校の例ですが、一般の企業にとっても大変参考になります。
- スーパーの客とトラブルになったレジ担当従業員から雇用主に対して安全配慮義務違反の主張がなされた事案。雇用主は、直ちに客を入店拒否にするなどの措置はしなかったが、客からの当該従業員の退職要求には応じなかったことや、入店拒否措置の可能性を客に伝えていたことなどから、安全配慮義務違反が否定された。(東京地裁平成30年11月2日判決)
- NHKの委託先のコールセンターで、応対者が頻繁にわいせつ電話や暴言等を受けていた事案。会社は、電話応対マニュアルや対応困難電話の転送体制などを整備していたことなどを理由に、安全配慮義務違反は否定された。(横浜地裁川崎支部令和3年11月30日判決)
会社がカスハラに対する方針と具体的な対策を定め、労働者に周知、徹底させることが大変重要だと言えます。
個人に任せず組織ぐるみの対策が必要な理由
カスハラ問題を個人に丸投げすると、対応にばらつきが生じるだけでなく、従業員の精神的負担が増大します。一人ひとりの従業員が適切な対応をできるとは限らず、結果的にトラブルが長引く恐れがあります。また、個人対応は企業全体のリスク管理の観点からも不十分です。従業員が適切に対応できず、顧客とのトラブルがエスカレートすれば、企業全体の信頼が損なわれることになります。
さらには、会社が適切なカスハラ対応を行っていない場合は、先述の裁判例にもあるとおり、会社の安全配慮義務違反が問われることも考えられます。
そのため、カスハラへの対応は、組織全体で統一した方針を定め、従業員に周知徹底して行う必要があります。これにより、従業員は個人の裁量に頼らず、安心して業務に従事できる環境を整えることができるのです。
会社が行う具体的な対策方法
厚生労働省が推奨するカスハラ対策には、以下のようなものがあります。
1. 会社の方針の策定と周知
カスハラに関する明確な対応方針を社内規定として文書化し、全従業員に共有します。全社員のみならず、顧客が確認できる場所に、会社の方針を示すポスターを掲示する方法もあります。
2. 相談窓口の設置
トラブル時に迅速に対応できる相談窓口を設け、従業員が安心して報告できる環境を整えます。
3. 対応マニュアルの整備
カスハラ発生時の具体的な対応手順を記載したマニュアルを用意し、従業員が迷わず対応できるようにします。
4. 教育研修の実施
従業員に対する研修を定期的に行い、カスハラの具体例や対応スキルを学ぶ機会を提供します。
5. 外部専門家の活用
必要に応じて弁護士やカウンセラーと連携し、法的支援やメンタルヘルスケアを行います。
カスハラは、従業員個人が会社に報告せずに、一人で抱え込んで対応しているケースも多々あります。従業員と会社を守るための対応マニュアルを作成する前に、従業員にカスハラに関するアンケートを取り実態を把握することもおすすめいたします。実態を把握し、それぞれの会社に則したマニュアルを作成することが大変重要です。
東京都のカスハラ指針
令和6年12月16日、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に基づき、東京都は「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を公表されました。
条例には、カスハラの定義は「①顧客等から就業者に対し、② その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、③就業環境を害するもの」と規定されています。
この対象となる就業者は、労働基準法の労働者はもちろん、その他公的機関職員(自治体、警察、消防、病院、学校、交通機関等)、社長・取締役・理事等、個人事業主、家族従事者、家内労働者、議員、インターンシップ生、教育実習生、ボランティア従事者、PTA役員、自治会役員等も幅広く含まれると、ガイドラインには明記されています。
東京都の条例には、罰則の規定はありませんが、カスハラの行為によっては、刑法の暴行罪、傷害罪、脅迫罪、恐喝罪、名誉棄損罪、侮辱罪などの罪に該当する場合があると記載されています。一方で、正当なクレームや、不当に制限されてはならない合理的配慮が必要な方の例、消費者の権利についても記載されており、正当なクレームと理不尽なクレームの判断方法も丁寧に記載されています。企業でのカスハラ対策においても大変参考になる内容です。
おわりに
カスハラは、従業員の健康や企業の存続を脅かす重大な問題です。企業は、個人に対応を任せるのではなく、組織全体で取り組むべき課題として捉え、具体的な対策を講じる必要があります。法令や指針を理解し、全従業員が安心して働ける環境を整えることが、企業の信頼と持続可能性を高める第一歩です。
厚生労働省のハラスメント総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、カスハラ対策に関するポスターや対応マニュアル、教育研修資料の無料ダウンロードや研修動画の視聴が可能となっています。積極的に利用し、1日でも早くカスハラ対策を進めていきましょう。