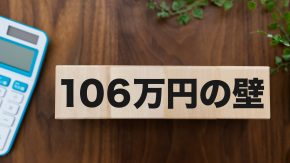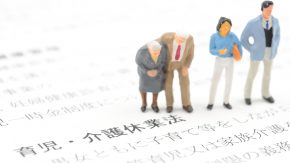井上 敬裕 氏
中小企業診断士・社会保険労務士
青果加工場の工場長を約9年間務めた後、40歳の時に中小企業診断士として独立。販路開拓支援、事業計画作成支援、6次産業化支援、創業支援などを行う。
平成27年社会保険労務士として開業し、現在は社会保険労務士として給与計算を中心に労務関連業務を行っている。
社会保険労務士法人アスラク 代表社員
https://sr-asuraku.or.jp/about/
現行の年金制度の課題
一般的に現行の年金制度は財源問題を中心に課題を抱えていることは広く知られています。しかし、ただ財源が確保されればよいというものではありません。給付の内容、年金と仕事のバランス、保険料の負担の仕組みなどの点で時代の変化とともに課題が生じています。年金制度の見直しは、財源的な視点だけではなく多角的な視点で進めていく必要があるのです。
現在、政府で審議されている次の3つの見直し案について見ていきましょう。
- 標準報酬月額の上限引き上げ
- 在職老齢年金制度の緩和または廃止
- 基礎年金の給付調整の早期終了
標準報酬月額の上限の見直し
厚生年金の標準報酬月額の上限は、平均標準報酬月額の約2倍である65万円に設定されています。しかし、近年の賃金上昇により、上限額を超える被保険者が増加しています。特に男性では約1割が上限に達しており、適正な保険料負担と給付の観点から、上限額の引き上げが検討されています。
現行の標準報酬月額制度
現在、厚生年金では標準報酬月額は全部で32等級あり、下限は8.8万円、上限は65万円となっています。健康保険では標準報酬月額は全部で50等級あり、下限は5.8万円、上限は139万円です。厚生年金の標準報酬月額の上限については、被保険者全体の平均標準報酬月額のおおむね2倍となるように設定されています。各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額がこの上限額を上回り、その状態が継続すると認められた場合、政令で上限を追加できるように定められています。
平均標準報酬月額の現状
厚生労働省によると、全被保険者の平均標準報酬月額は2022年3月末で327,278円、2023年3月末で329,472円です。平均標準報酬月額の2倍に相当する額はそれぞれ654,556円、658,944円となっており、上限の65万円を上回っています。
上限該当者の分析
第1号厚生年金被保険者で標準報酬月額の上限の等級(65万円)に該当する人の割合は6.5%で、健康保険と比べ、多くの人が上限の等級に該当しています(健康保険では1%未満)。男性の第1号厚生年金被保険者で標準報酬月額の上限等級(65万円)に該当する人の割合は9.6%(243万人)で、上限等級が最頻値になっています。
厚生労働省の提案内容
厚生労働省では以下の案が出されています。
| 案 | 上限額 | 目標とする上限該当者割合 | 特徴 |
| 第1案 | 75万円 | 4%以下 | 男女とも最頻値にならないよう設定 |
| 第2案 | 79万円 | 3.5%以下 | 男性上限該当者を半減 |
| 第3案 | 83万円 | 3%以下 | 全体の上限該当者を半減 |
| 第4案 | 98万円 | 2%以下 | もっとも大幅な引き上げ |
在職老齢年金制度の見直し
65歳以降も働き続ける高齢者が増加するなか、現行の在職老齢年金制度では、収入が一定額を超えると年金支給額が減額される仕組みとなっています。この制度により就労意欲が抑制されるといった課題が指摘されており、高齢者の就労促進の観点から制度の見直しが検討されています。
制度の基本的な仕組み
在職老齢年金制度は、現役世代の負担が重くなるなかで、報酬のある者は年金制度を支える側に回ってもらう という考え方に基づく仕組みです。賃金と老齢厚生年金の合計額が50万円を超えると、年金支給額が調整(合計額から50万円を差し引いた額の2分の1が支給停止)されます。また、老齢厚生年金は65歳になれば受給権が生じますが、70歳未満で在職の場合は保険料を負担しなければなりません。
現状の課題と問題点
2022年度末に在職している65歳以降の年金受給権者は308万人で、その16%に当たる50万人が支給停止の対象となっています。支給停止者数は9年前の2013年度末と比較して約24万人増加しています。内閣府の調査では、「厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方」の問いに対し、「年金額が減らないよう時間を調整し会社等で働く」と回答した人の割合は44.4%でした。働く意欲や能力があるにもかかわらず、就労継続を希望しない、勤務時間を短縮する傾向が見られ、中小・零細企業の人材確保・定着にマイナスの影響を与えています。
国際比較における位置づけ
諸外国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス)と比較すると、年金支給開始年齢以降、収入額によって年金給付額を減額する仕組みが存在するのは日本だけです。国際競争力の面から見ても課題があります。
見直し案と期待される効果
このような現状の課題を考慮して、厚生労働省は以下3つの案を提示しています。
| 案 | 内容 | 期待される効果 | 支給停止者数の予測 |
| 廃止案 | 制度の完全廃止 | 就労抑制の解消 | 0人 |
| 緩和案1 | 基準額を71万円に引き上げ | 支給停止者の大幅減少 | 約23万人 |
| 緩和案2 | 基準額を62万円に引き上げ | 支給停止者の段階的現象 | 約30万人 |
基礎年金の給付調整の見直し
現行制度では、マクロ経済スライドによる給付調整により、基礎年金の伸びは2057年まで抑制される予定となっています。しかし、今後の物価上昇に対応するため、調整期間の大幅な短縮が検討されています。この見直しは、厚生年金の積立金を活用することで基礎年金受給者の生活水準の維持を目指すものです。
マクロ経済スライドの現状
現行の年金制度では、マクロ経済スライドによる調整(少子高齢化が進むなかでも持続可能性を確保する仕組み)が行われています。賃金や物価の伸びより年金額の伸びが抑えられており、現役世代の保険料の負担が大きくならないような仕組みになっています。しかし今後は継続的な賃金や物価の上昇が想定されるため、基礎年金額が物価や賃金の上昇に追いつかなくなる可能性が高まっています。そこで、基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整を早期終了することが検討されています。
給付調整の早期終了案
年金の給付は基礎年金(1階)と比例報酬年金(厚生年金、2階)の2階建て構造になっています。現行ではマクロ経済スライドによる年金額の給付調整を厚生年金は2026年で終了、基礎年金は2057年まで継続する予定です。しかし、基礎年金額の給付調整も厚生年金と同じ2026年に終了させれば、物価や賃金の上昇に連動した給付水準の上昇効果を実現できると考えられています。
財源確保の方向性
年金額の上昇に必要な財源については、財源的に安定している厚生年金保険料の積立金からの拠出を増やすこととされています。
まとめ
標準報酬月額、在職老齢年金制度、基礎年金の給付調整に関する3つの見直し案を見てきましたが、最終的にはどうしても財源的な問題に行きついてしまうようです。
今回の3つの案以外にも、企業規模に限らない適用拡大や第3号被保険者制度の見直し、保険加入上限年齢の引き上げ等も検討されており、今後の年金制度の行方は目が離せない状況です。